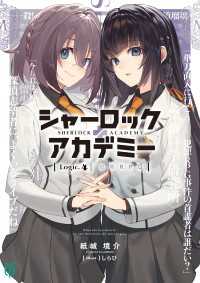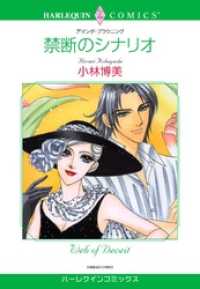内容説明
「パンのための学問」と揶揄されることもある法律学を、その出自から掘り起こすと同時に、他の人文=社会諸学との関連のなかで捉え直すことを通じ、単なる資格取得や実用のための手段にとどまらない「制度的想像力の学」として提示する。グローバル化やリスク社会における新たな法秩序、社会改革の可能性を考える。
目次
1 法学はどのようにして生まれたか(なぜ法の歴史について学ぶ必要があるのか;西洋法の歴史)
2 生きられる空間を創る―法学はどんな意味で社会の役に立つのか(法に期待される役割と背景にある思想;活動促進と紛争解決―民事法の役割 ほか)
3 制度知の担い手となる―法学を学ぶ意味とは何か(法学を学ぶ意味とは?;法的思考のいくつかの特徴―哲学との対比 ほか)
4 法学はいかにして新たな現実を創り出すのか―法学と未来(法的思考で現実は変えられるか;難事案をどのように判断するか(一)―ドゥオーキンの構成的解釈 ほか)
5 法学を学ぶために何を読むべきか
著者等紹介
中山竜一[ナカヤマリュウイチ]
1964年生。京都大学大学院法学研究科博士課程中途退学。現在、大阪大学大学院法学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。