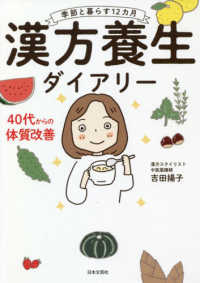内容説明
偏見と体の不自由のなかで、町をさまよい喜捨を乞う病者を強制収容する「らい予防法」は一九〇七年に施行された。本書はほぼ半世紀のち、一九五五年の国立施設などを、そこに暮らす人々自らが撮影したものである。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
85
2016年907冊め。全国のハンセン病療養所から集められた写真をまとめた記録集。意外なほど淡々としていて悲劇的な側面は強調はされていない。これは特効薬開発後の時代の写真が主だからだろうか。文学作品で読みかじった療養所のすさまじいばかりの悲壮さとは受ける印象が違う。しかし慰問に来ている元皇族が、畳の上でも靴を履いているのを見ると、彼らのおかれた境遇だとか世間の偏見等が全く解消されていないと感じさせられる。舌で点字を読んでいる全盲患者の写真にも驚かされる。2016/10/28
ののまる
5
「無関心があやまちを生む」2019/05/20
芋堅干
1
大学の授業で。小さな閉ざされた社会のなかでも、立場によって希望が生まれたり、反対に今の生活への諦めが生まれたりすることが興味深かった2010/07/15
まちこ
0
1956年発行の療養所写真集。結核もあるがおもにハンセン病。べつにショッキング画像なんかなんにもなく、知られざる療養所の穏やかな生活が続く。盲目の老人が3人、杖を持ち互いの肩に左手を掛けて歩いている画像が印象的だが、これも当事者達によれば「売らんかなの盲人画像」に思えるらしい。この時既にハンセン病は治る病気で、包帯の人など誰もいないにも拘らず、らい予防法はこの後40年も続いた。巻末の当事者の弁「この病気は治るということが徹底的に普及しなければ、一度病んだ私をやすやすと社会は受け取ってくれません」が重い。2024/09/10
@第2版
0
北條民雄の延長として初めて本著のような写真文庫に食指を伸ばしてみた。想像していたより穏やかな写真が多くて、ハンセン病そのものというより療養園の日常生活に注目したものが大半を占めていた。50年代ということでまだまだ現代的設備の乏しい園内は、木造平屋の林立する時代がかった風景で、当時のイメージのない私にとってはどれも貴重な資料だった。また、最後のページに掲載された入園者による本著に向けた批評文がどれも切実なもので、ここだけでも読む価値が十全にあった。2018/04/19