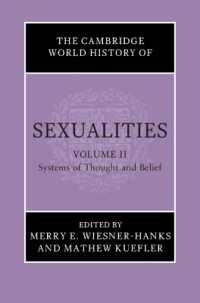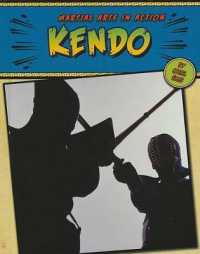内容説明
中国は「人治」の国で、「法治」は軽んじられているというのは本当か?中国が近代法を獲得するまでの過程・現状・課題を追って検証する。
目次
第1章 中国近代法史序説
第2章 西洋近代型法制への転換
第3章 中華民国法制整備
第4章 近代史上生じた特殊な地域の法
第5章 政治に翻弄される中華人民共和国法
第6章 現代中国における立憲主義―その現状と課題
第7章 現代中国の「司法」
第8章 現代中国における市場経済を支える法
おわりに―中国にとって法とは何か
著者等紹介
高見澤磨[タカミザワオサム]
1958年生まれ。東京大学東洋文化研究所教授、博士(法学)。中国法
鈴木賢[スズキケン]
1960年生まれ。北海道大学大学院法学研究科教授、博士(法学)。中国法・台湾法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sapporo Shiojiri
3
文字通り近代中国にとっての法が、その性質を転換させていく過程を叙述した本。 ❡東アジア近代における、法にかかわる大きな出来事①近代国家の条約に出会いほかの主権国家なるものを認知した。②国際法および社会進化論に出会ったことが、制度や理念自体を改めない限り生存を図ることが危ういという意識を高めた。❡社会進化論はまだ分かりますが、国際法がここまで危機意識を喚起するものであったというのは驚きでした。 2020/08/07
セイタ
2
法という視点から中国を解剖している法!日本の地理研究では珍しい。前半は法制度史となっている。しかし、法制度史を述べているはずが、世界史で習ったような政治のことにまで言及している。それは中国の法が政治の影響を強く受けたからである。その悪習は現在も続いており、法制度は党の道具と化している。前半は面白くなかったが、後半の現在の中国で法がどのような役割を果たしているのかを述べる章はかなり面白かった。とくに「影響性訴訟」という言葉が気になった。吳革の「中国影響性訴訟」読んでみよう。社会変革の一矢になるかもしれない。2015/09/12
denken
1
「市民の権利へ」はおそらく筆者の願いなのだろう。叙述のなかで,あくまでも主流は「統治の道具」であることがはっきりしている。中国人民大学がそれなりに偉いのは知っていたけど,ここまで北京大学の出番がないのは予想外。劉暁波がまだノーベル平和賞を受賞していない時期に出版された。惜しいことをしたものだ。劉暁波と零八憲章についても触れられている,淡々と。もっとも,後出しジャンケンで意見だされるよりも余程参考になる気はする。まだまだ難しい民主化よりも,まずは憲政をしっかり行うことが当面重要なのだとさ。2010/10/29
Tetsuya Noguchi
0
近現代中国にとって法とは何かを歴史学の観点から記述したもの。個別の法律に関する解説書では無い。 私の場合、香港の「一国二制度」を研究する一環で、英国のコモンローと中国の法思想を比較する上で、この本は大変重宝した。2018/12/20
-

- 洋書
- The Ruffians