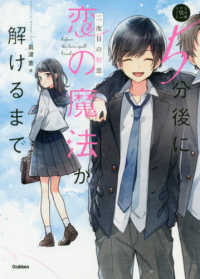出版社内容情報
<私>という意識の根が、認知科学や脳科学の新しい知見によって揺らいでいます。統合された<私>の位置と、ヒトが人であることの根拠を、精神史の連続と断絶のドラマに探ります。古代中世の叙事詩と哲学との関係に潜む、知られざるアイデア。
内容説明
謎と発見に満ちた思想史への旅。魂への態度、そして世界と向かい合う構えの伝承を追って、ギリシャの詩と哲学から、中世神学の世界へ、デカルトとイエズス会士たちへと、誤読と誤訳の痕跡をたどります。中世と近代、西洋と中国・日本、異なった世界像の池に投げ込まれたアイデアが描く不思議な波紋―知らなかった近代の横顔が見えてきます。
目次
第1日 はじめに「機械の中の幽霊」
第2日 アキレウスには意識も意志も存在しない?
第3日 魂の一体性と部分―ソクラテスからプラトンへ
第4日 メデアは理性のゆえに狂った―「葛藤」と「振動」
第5日 「憐れみ」の否定から肯定へ―アウグスティヌスにおける「心臓」と「横隔膜」
第6日 「舟と船人の比喩」―一六・一七世紀東アジアへの『魂論(デ・アニマ)』導入
第7日 もう一つの「舟と船人の比喩」―『魂論(デ・アニマ)』崩壊以後
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
那由田 忠
13
魂が何を指しているのか。精神的なものだけか、感情のようなものを含むのか。この問は、魂と身体との関係がどうなっているのか、という問に連なる。今の科学観で無意味としても、昔の哲学を読み解くには不可欠の観点ではある。その意味でとても面白い指摘が多々ある。しかし、残念ながら、話がどんどん脱線してオタク的な細かい引用をする上、図を使って、あるいは簡単なまとめで簡潔に整理してくれないので、要は全然わからないということになってしまうのだ。困ったもんだ。2017/05/09
すずき
4
ホメロスからアウグスティヌスまでの古代を中心に後年の宣教師によるアジアへの布教なども取り扱い〈アニマ〉を考える。最後にバーナード・ウィリアムズがちらっと登場するのだが、著者は『現代倫理学事典』のウィリアムズの項も執筆しており、『不道徳的倫理学講義』で詳しくウィリアムズを紹介する古田徹也氏と一時期専修大で同僚だったはずである、いかなる事情か。中身に関しては不勉強な私程度がどうこう言えるレベルではない。これほど面白い本を書く著者が数少ない著作(訳は多い)を残して既に亡くなられていることは本当に悔やまれる。2019/11/23
左手爆弾
4
博学な著者の本領が良く出ている。このシリーズは入門書的な内容のものが多いが、本書に関してはかなりレベルが高く、要約は不可能といっていいほど、内容が富んでいる。魂とも、心とも訳せるアニマの語をギリシア・ローマの古典を中心に探っていくのだが、つまるところ目指しているのは、我々が自らの「心」を意識するようになったのはいつ頃、どのようにしてなのかという問いだ。最初の「アキレスには心はなかった」みたいな問題は、我々に様々なものをつきつけるだろう。2015/04/06
takao
3
ふむ2024/02/13
メルセ・ひすい
2
10. 12 講演録 謎と発見に満ちた思想史への旅。魂への態度、そして世界と向かい合う構えの伝承を追って、ギリシャの詩と哲学から、中世神学の世界、デカルトとイエズス会士たちまで、誤読と誤訳の痕跡をたどる。2008/06/02
-
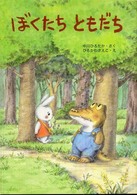
- 和書
- ぼくたちともだち