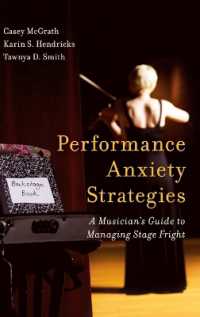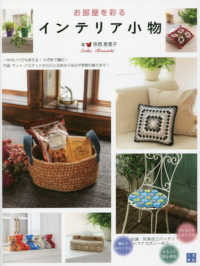出版社内容情報
伝統的な国学を基盤とし,西洋の文法概念が折衷された国文法.その国文法と,従来疎遠な関係にあった生成文法や,記述研究としての日本語学,近年の歴史語用論,社会言語学等の理論を包括的に踏まえ,日本語文法史を捉えようとする画期的な試み.形態論,統語論,接辞,代名
内容説明
伝統的な国学を基盤とし、西洋の文法概念が折衷された国文法。その国文法と、従来疎遠な関係にあった生成文法や、記述研究としての日本語学、近年の歴史語用論、社会言語学等の理論を包括的に踏まえ、日本語文法史を捉えようとする画期的な試み。形態論、統語論、接辞、代名詞、直示・人称指示、語用論的ルールといった観点から分析し記述する。
目次
第1章 文法史とは何か(文法はどこにあるか;国文法;生成文法;社会言語学・文法化・歴史語用論;新しい歴史文法研究と今後の展開)
第2章 述部の構造(活用;テンス・アスペクト;ムード・モダリティ)
第3章 統語論(統語論から見た活用;格と文法役割―「の」「が」「を」;活用と統語構造の変化;準体句およびその周辺の構造;係り結び小史;結論)
第4章 係助詞・副助詞(係助詞・副助詞の生起環境;格助詞との前後接;付加節と係助詞・副助詞;係助詞・副助詞の形成過程)
第5章 直示と人称(人称に関わる現象の歴史的変化;指示代名詞・指示副詞)
著者等紹介
金水敏[キンスイサトシ]
大阪大学大学院文学研究科教授
高山善行[タカヤマヨシユキ]
福井大学教育地域科学部教授
衣畑智秀[キヌハタトモヒデ]
福岡大学人文学部講師
岡崎友子[オカザキトモコ]
就実大学人文科学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。