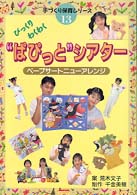内容説明
15世紀に出発し、今なおわれわれがその中にいる「世界システム」を、国民経済の枠をこえた「ヨーロッパ世界経済」の展開過程としてとらえるジャンボ・ヒストリー。このシステムが危機を迎えている現在、その生成史をふりかえることは、現代社会の危機を根源的に問い直し、新しい社会理論を構想するための必須の作業であろう。
目次
はじめに―社会変動の研究のために
1 近代への序曲
2 新たなヨーロッパ分業体制の確立―一四五〇年頃から一六四〇年頃まで
3 絶対王政と国家機構の強化
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月世界旅行したい
5
いまさら読む2017/07/11
Francis
3
名著として有名な本。最近読んだ水野和夫氏や柄谷行人「世界史の構造」がこの本に触れていたので、積ん読状態から引っ張り出して読んだ。(「世界史の構造」は内容の大半がこの本の要約に近い。)今の資本主義につらなる近代経済システムの発生を14世紀以降の西ヨーロッパの経済・社会を分析していくことで考察していく。難しいと思っていたが、わりとすらすらと読めた。面白い。2014/11/06
koji
3
ウオーラーステインは、世界経済を構成する中核、半辺境、辺境が、固有の経済的役割をもち、それぞれ階級構造を発展させ、独自の労働管理の方式が成立したと言っています。政治も、中核地域の国家は中央集権化がもっとも進行したといっています。現代思想の潮流のひとつであるアナール派が基礎になっており、難しいところもありますが、何とかくらいついていきたいと思います。2010/05/15
鏡裕之
2
ウォーラーステインは、世界システムという考え方を提示している。世界システムとは、一国家単位のものではない。複数の国家、複数の文化を含んだ単位であり、その範囲内で単一の分業が行われている。世界システムには、ローマ帝国のような世界帝国と、近代になってヨーロッパで発生した世界経済がある。本書は、その世界経済=近代世界システムについての本である。15~6世紀にかけてどのようにしてヨーロッパ全体で分業が進んでいくのかを丁寧に解きあかしてくれる。1度目の読書ではうるさいだけだが、2度目では全体像が浮かび上がる。 2013/06/01
金糸雀
2
ほんの少しの差が埋めがたい構造になった,という表現は進化ゲームを誘ってるんでしょうか.ぜひモデル化したいですね(ゲス顔