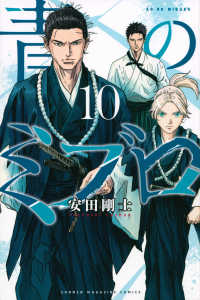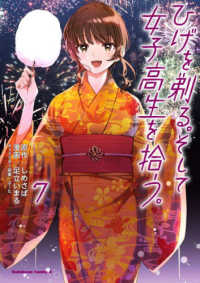内容説明
中世は儀礼と象徴に満ち溢れた世界だった。それらは宗教と政治の場や社会的秩序の形成において決定的役割を担っただけではなく、身振りや感情表現に形を与えていた。また、社会に溢れる数々の象徴も身分社会を表象する連帯と排除の記号として機能した。儀礼行為と象徴の分析から、中世世界の深層にある原理をあぶり出す。
目次
序章 「カノッサの屈辱」は出来レースだったのか
第1章 支配の道具としての儀礼
第2章 家族とその転生
第3章 身振りと感情表現
第4章 連帯と排除の記号
第5章 象徴思考の源泉
結論 儀礼と象徴のヨーロッパ
著者等紹介
池上俊一[イケガミシュンイチ]
1956年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科西洋史学専攻博士課程中退。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。研究テーマはフランスとイタリアを中心とするヨーロッパ中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
8
社会を形作る確たる制度が未発達であった中世期において、秩序を維持するための儀礼やそこで使われた身振り、象徴について考察した一冊。ローマ帝国由来・ゲルマン人由来の儀式・儀礼がキリスト教化されていく中で、数や色、身体にも宗教的な意味付けがされていくのは面白い。また対抗関係にあった教皇・皇帝・国王の三者が、互いに式典を真似ながら、それぞれの権威を高めあっていたという指摘も興味深い。儀式や式典が王の権威を「誇示」するのでなく、「創造」していた時代であったことがよくわかる。2018/06/12
陽香
1
200812192017/11/09
児玉
0
儀礼・儀式の面より、中世の時代区分を説明しようとする姿勢が面白かった。 本シリーズ「ヨーロッパの中世」は、どれを読んでも新しい発見と閃きを与えてくれるので、読んでいて飽きる事が無い。2015/03/10
小池馨子
0
もっと早くに読んでおくべきだった。2011/11/15
カコ
0
言葉遣いは硬いけど、中世って面白いなあ、と思う。去年のパスタの授業みたいにネタの宝庫。 特に面白かったのは数・色の象徴。 教会が掲げたモデルとして、「子孫を残すことのみを目的とする正式の夫婦間での、しかも時と場所・体位をわきまえた性交渉のみが容認」とあったんだけど、体位というところで笑った。悪しき体位を取ってしまった場合って、悔い改めて許してもらえるの?ww時処位を弁えることは何においても大事だとは思うけど。2011/03/23
-
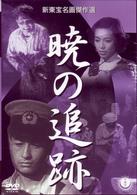
- DVD
- 暁の追跡