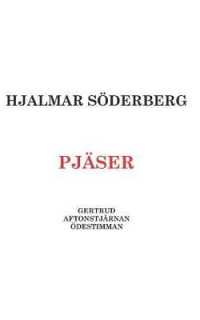出版社内容情報
何度も聴いた噺なのに,なぜ,また笑ってしまうのか.奥の深い落語の魅力について,桂米朝,柳家小三治,山田洋次が語り尽くし,延広真治・川添裕・小谷野敦・荻田清・武田雅哉・長井好弘・中込重明・今岡謙太郎らが書き下ろす.
内容説明
落語は、なぜおもしろいのだろう。おなじ噺を何度聴いても、なぜおかしいのか。ひとり語りの芸に、なぜ引き込まれるのか…。本冊では、四〇〇年の歴史をもつ古典芸能ならではの、落語のふしぎな魅力を解きあかす。読めば落語がもっと楽しくなる、落語好きのためのシリーズ、第一冊。
目次
桂米朝師匠に聞く
落語はなぜおもしろいのか(落語はなぜ凄いのか;『らくだ』が居る場所;上方落語の特質;円朝のネタさがし;落語・講談と歌舞伎;落語―中国からの視点;落語の生成―かつぎや・しの字嫌い;猿後家;資料復刻 條野採菊『落語』)
対談 落語をめぐって
インタビュー 柳家小三治
データ編(そもそも茶話―落語のみなもとは;落語三万二千席―二〇〇二年・寄席ネタ帖全調査)
著者等紹介
延広真治[ノブヒロシンジ]
1939年生。近世文学。帝京大学教授、東京大学名誉教授
山本進[ヤマモトススム]
1931年生。芸能史研究
川添裕[カワゾエユウ]
1956年生。日本文化史、メディア研究。皇学館大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
21
笑えない時代に笑いをとることは至難の業だと私は思う。11年前の本。 小谷野敦先生は、能楽や茶道や歌舞伎や浮世絵まで知っていて落語を知らないというのはなかろうと指摘される(48頁)。高級芸術、低レベルなどという仕分けもあるが、何をもって質を決めるか、意外にも線引きや基準が不明かもしれない。中世の平曲、説教節、古浄瑠璃、近世浄瑠璃、太平記読み、講釈、講談まで、読みの中から落語も成立という(51頁)。1911(明治44)年、落語日曜会第百回記念「落語演題見立番附」『落語系図』(98頁)は相撲の番付のようである。2014/11/02
ZEPPELIN
3
落語の入門用。ではないらしい。最初の桂米朝さんへのインタビューは面白い。ぜひこの人のネタを聞いてみたいと思わせる話し振りがいい。ただ、そのあとに続くどこかの教授や研究家たちの話が冗談抜きにつまらない。「落語は素晴らしい。なぜなら、落語は素晴らしいからだ」とでも言いたげなアホくさい文章が続く。ここで一気にこの本の価値がゼロとなる。こちらが聞きたいのは学者の腐った回顧録ではない。米朝さんと小三治さんへのインタビューのロングバージョンだけで本を出した方がずっといい出来になったと思う2014/03/25
Kazuo Ebihara
1
本書は、20年前に発行された全3巻の『落語の世界』シリーズ第1弾。桂米朝師、柳家小三治師、山田洋次監督へのインタビューと落語のルーツに関する様々な歴史的考察がされています。 最終章では、長井氏が2002年の東京の定席4軒のネタ帖を集計、分析。その数32,000席。よく掛かるネタ50をランキング。長井氏は2008年に『新宿末広亭のネタ帳』を上梓し、7年間のネタを集計分析しています。今日の状況は、何処かに載っているのかな。毎月、毎年の定席のネタと出演者の状況を集計分析し、ネットで公表してくれたら見るのにな。 2023/12/24