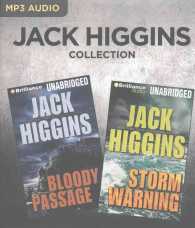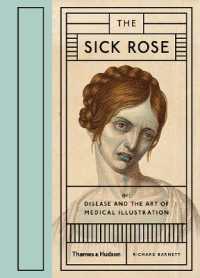出版社内容情報
尖った先端を紙などに押し当てて凹ませ、文字や符号や絵を書く道具、角筆。その見えにくさという性質から、鉛筆の普及以前には、漢籍や仏典の訓点、下書き、秘密の記録など多様に用いられていた。半世紀以上にわたり日本全国および中国・韓国で数多くの角筆文献を掘り起こしてきた著者が、角筆の世界のもつ広がりを解き明かす「文字の文化史」。
内容説明
「角筆」とは、尖った先端を紙などに押し当てて凹ませ、文字や符合や絵を書く用具であり、書かれたものが見えにくいという性質から、鉛筆の普及以前には、漢籍や仏典の訓点、下書き、秘密の記録など多様に用いられていた。半世紀以上にわたり日本全国および中国・韓国で数多くの角筆文献を掘り起こしてきた著者が、角筆の世界のもつ広がりを解き明かす“文字の文化史”。
目次
第1部 日本国内での発見(白紙の手紙―高野長英脱獄の意志表示;白紙の記録―記録に託した真情;白紙の遺書―平井収二郎角筆に込めた真情;江戸時代の全国の方言―方言史をひらく ほか)
第2部 東アジアへの広がり(労幹先生―漢代木簡の角筆文字を追う;敦煌文書の角筆文字―中国の角筆紙文書;韓国の角筆文献―ヲコト点の源流;角筆で書いた新羅語の発見―片仮名の先蹤)
著者等紹介
小林芳規[コバヤシヨシノリ]
1929年山梨県生。東京文理科大学文学科国語学国文学専攻卒業。広島大学教授、徳島文理大学教授などを歴任。広島大学名誉教授。文学博士(東京教育大学)。専攻は国語学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Miyaz