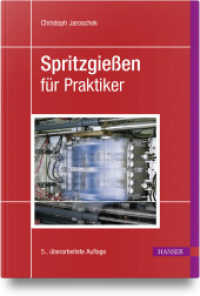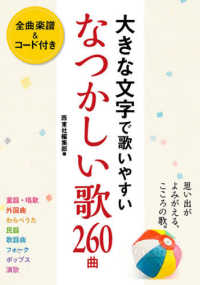出版社内容情報
もの忘れはなぜ起こるのか.認知症をどのように理解したらよいのか.人の一生を,記憶の生成と喪失の過程ととらえ,記号論の観点から認知機能のメカニズムを明らかにする.これまで医学,実験心理学,情報処理理論を中心に研究されてきた「もの忘れと記憶」の仕組みに,記号論的視角から新たな光を当て,人間存在の本質に迫る.
内容説明
人が生まれ、言語や文化を身につけ社会的存在になり、やがて年をとり自然的存在に回帰していく過程、すなわち人間の一生について、記号論の考え方から考察すると、その姿はどのように描けるだろうか。これまで医学、実験心理学、情報処理理論を中心に研究されてきた「もの忘れと記憶」の仕組みに、パースをはじめとする「解釈の記号論」の視角から新たな光をあてる。
目次
1 記号と記号論(記号とは何か;記号研究の歴史 ほか)
2 記憶の条件(生物学的条件;社会的環境と記号の階梯 ほか)
3 言語文化の習得(音楽のように・絵のように・ダンスのように;言語文化の習得 ほか)
4 加齢による「もの忘れ」(忘れにくいこと;忘れやすいこと ほか)
5 つながる記憶(「もの忘れ」と認知症;解釈の習慣と記憶―物質から生物までの連続性)
著者等紹介
有馬道子[アリマミチコ]
1941年生まれ。大阪市立大学大学院文学研究科修士課程修了。英語学・言語学・記号論専校。現在、京都女子大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
13
『一般言語学講義』においてソシュールは「社会生活における記号の生を研究する学」としてセミオロジーを定義(13頁)。記号の三項関係という図式がある(44頁)。点としての質。線としての関係。そして三角形としての表象。サピアは、概念は経験のスライディング・スケールであるとし、概念が生活上の必要性に応じてかたちを変えると考えた(74頁)。文化とは「慣習的な解釈の仕方」であり、言語と文化は切り離せない関係にある(75頁)。合点。人間の発達は、味・触・嗅―聴―視と進む(96頁)。衰えるのは逆の道。老けたくないなぁ。2014/02/09
袖崎いたる
9
パースはポストモダンである、的な趣向。概略からはじまりヒポクラテスが実は記号論の起源(そうだったのか!)であってソシュールは記号を二項関係で捉え、その後いろいろあってパースは三項関係に至ったのだけどこれがマジパネーということを押さえ、肝心のもの忘れと記憶の問題にゆく。本来の言語習得の過程だと類像性、指標性、象徴性と経るところがアルツハイマーを典型としたもの忘れの状態だとその過程の逆立ちが起こるとし、その観点から時間と場所と人物の感覚が記号的な解釈志向の濃度によって構成されているものと見る。一つの常識分析。2017/03/25
くれは
3
人間の認知は (1)事象に対する直観的・生理的な「感情」 (2)事象間の反応や関係を捉える「注意」(3)観念や習慣を媒介に事象どうしを結びつける「概念」の順に発達し、加齢による物忘れ(認知能力の劣化)はこの逆の過程を経る、というのが要旨。あとがきに引用されている「もうろくをとおして 心にとどまるものを 信頼する。 もうろくは濾過器。」という詩が本書の主張ををとてもよく要約していると思う。人間に固有のアブダクション(仮説的推論)がどのようなメカニズムで起こるのかについても説明があると嬉しかった。2012/09/10
かんちゃん
2
加齢によるもの忘れを記号論の観点から説明できないか、という議論で、面白い試みだと思った。前に記号論の本を読んだ時は何を言っているのかさっぱり理解できなかったけど、何かしらの状況に落とし込むことでなんとなく言わんとするところ(のほんの少し)が分かった気がする。人が自然的存在から、社会的存在になるにつれて、習慣はしだいに物理法則(当たり前のこと)になっていくが、歳をとるにつれて再び自然的存在に近づき、習慣が「ゆるむ」ことによってもの忘れが起こる。実際の所はよく分からないけれど、興味深い議論。2012/12/16
hideko
1
記憶と物忘れを記号論から解釈。私は言語の働きを記号論から解釈したところが興味深かった。そして、内容とは離れるけど「総合的な深い勘」仮説的推論(アブダクション)=与えられた状況(結果)を見ながら知識(規則)を発見的に利用して類推。創造性がある。…が経験知と共通していて使えると思った。2012/10/14