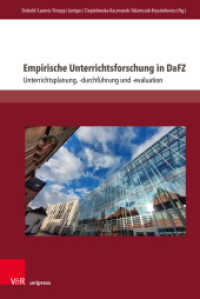内容説明
水俣病の淵で、輝く人々。当時、衝撃とともに受けとめられた写真と、30年を経て甦った秘蔵の写真の数々を、思いを込めて編み上げた希有な記録。
目次
すべてはここから始まった
海辺に生まれて
初めて出会った患者
宝子
半永君の帰宅
野球少年
闘う
歳月
著者等紹介
塩田武史[シオタタケシ]
1945年香川県高松市に生まれる。法政大学社会学部卒。在学中はカメラ部に所属。新聞の報道にふれ、水俣を始めて訪れたのは在学中の1967年夏。翌年も同地に入り、写真を撮り始める。卒業後の70年に水俣に移住。『アサヒグラフ』を中心に写真を発表。71年銀座ニコンサロンで初の個展を行う。72年結婚。73年には『塩田武史写真報告水俣’68‐’72深き淵より』(西日本新聞社)を出版。16年間の水俣住まいを経て、85年以降は熊本市で写真企画関連の会社を営む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
定年(還暦)の雨巫女。
12
《私-図書館》【再読】水俣でおきた、実際にあったこと。そして、終わってないこと。忘れてはいけないこと。繰り返さないこと。2025/10/22
勝浩1958
6
水俣病が市民の気持ちを二分したことを知りました。患者や漁民側に付くものと会社側につくものとに。そして、とても怖い写真が掲載されていました。その写真には「線路の引き込み線上に座り込んだ漁民たちに対し、工場を守ろうとする側のチッソ第2組合員たち」の威圧するような視線とふてぶてしい様子が鮮明に写しだされています。そして、水俣病に係る裁判はまだ終わっていないことを知りました。国・県・チッソは解決しようという意思はあるのでしょうか。わが国にはやるせなくなるようなことがまだまだたくさんあります。2014/07/05
まると
3
水俣病についてはかなり詳しい方だと思っていたが、収められた写真をつぶさに見ていくうちに、自分はこの理不尽な出来事を真に理解できていたのかと煩悶した。水俣を愛し、そこに住む人々と人間的に交流して寄り添わなければ、こうした写真は撮ることができない。写真を撮ることへの著者の罪悪感も文章から透けて見えるが、このとてつもない現実を記録として残すことへの義務感がそれを上回ったということだろう。補足する文章も、時に涙なくして読むことができない。これこそジャーナリストの仕事。若い記者にぜひ手に取ってもらいたい一冊だ。2018/08/23
マカダミアナッツ
3
歴史の教科書でみた水俣病患者とは違った姿がそこにあった。単に患者としての水俣病の人々ではなく水俣で生まれ、生き、そして亡くなっていった沢山の人たちの生活が写真の中に映し出されていた。時に涙し、怒り、笑う。撮ったカメラマンの被写体に対する愛情が感じ取れるような写真だった。公害の実態を知るにつれ今現在まさに高度経済成長の只中にある中国やアジアの国々の公害対策のずさんさが心配になる。13歳の少女に「(私は)結婚できない。水俣病だから」なんて、そんな悲しい言葉を言わせてしまうことはもう二度とあって欲しくない。2012/01/19
黒豆
2
2008年の発行。水俣に移り住んだという塩田さんの写真集。水俣病で苦しむ患者さんたちの日常の、輝く瞬間を撮っている。水俣を忘れてはならないと思う。2019/01/17
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢は王子の本性(溺愛)を知らない…