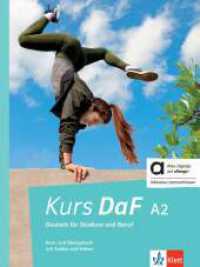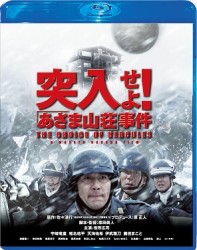感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メルセ・ひすい
1
11-48赤11 ★5 学術書 お勧め 国際的な経済・金融危機と、アメリカ単独行動主義の破綻にオバマ新政権はどう対処するのか。第二次世界大戦後、アメリカが他国とともに構築してきた世界秩序の経験を検証し、マルチラテラリズムの回復を提言する。2009/03/11
Keisuke Hosoi
0
かの有名なembedded liberalismの概念を持ち出したラギーの著書。論文が難しすぎたので邦訳版の啓蒙書を読む。それでも難しかった。結局embeddedされていたマーケットが「埋め込み解除」されつつあって、国際的な経済自由主義と国内的な社会的利益の追求の妥協をする仕組みが必要とかなんとか。それをどうするかは不明。日本の貿易黒字は一種の国際的規範である「産業内貿易」でなく「産業間貿易」なので、スーパー301条は許されるといったあたりが、彼の「妥協の仕組」の具体例を解くカギかもしれない。2012/10/13
メルセ・ひすい
0
訳書のため 新しさがない。イラク戦以前の書 今やG2の時代 これで米国が経済でこければ・・・・ 中国が米国債を処分すれば・・ $崩壊・・ デノミ⇒AMEROの再燃が・・・2009/04/22
メルセ・ひすい
0
※は指摘します。本書は。世界各地の安全保障や自由貿易の維持に、アメリカが積極的に関与するような第二次世界大戦後の国際制度と、その後の変容を解明し、「権力協調」や「権力の共同体」という安全保障の考え方、「埋め込まれた自由主義」という貿易と通貨・金融に関する考え方を見事に示している。2009/04/30
メルセ・ひすい
0
ユニラテラリズムからマルチラテラリズムへの変化と、世界に対する「アメリカの関与」を理解する要点が示されていまる。ラギーは冒頭に,フランクリン・D.ルーズベルトの演説を引いている、その演説は、真珠湾攻撃の数日後に行われたが、安全保障に関して、もはや距離を当てにできないと強調している、アメリカがヨーロッパと違って、勢力均衡による外交になじまず、その地理的・歴史的な「例外主義」の姿勢から国際的な役割を拒んだが、最後は、その「理想主義」を根拠として、ヨーロッパやアジアの戦争に介入したことをラギーは※2009/04/28
-
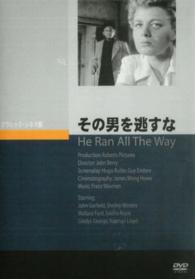
- DVD
- その男を逃すな