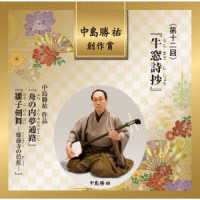内容説明
サンスクリット語などインドの言葉が原語であった仏典は、中国の文字や言葉に翻訳されて伝わることにより、東アジアの文化的基層となった。鳩摩羅什や玄奘ら、高僧たちの翻訳理論とはいかなるものか。どのような体制で、どれくらいのスピードで行われたのか。中国に無かった概念をどう訳したのか。さらに、中国で作られた、「偽経」とは?仏典の漢訳という、人類の壮大な知的所産を、専門外の読者にもわかりやすく解説した、初めての本。
目次
第1章 漢訳という世界へのいざない―インド、そして中国へ
第2章 翻訳に従事した人たち―訳経のおおまかな歴史
第3章 訳はこうして作られた―漢訳作成の具体的方法と役割分担
第4章 外国僧の語学力と、鳩摩羅什・玄奘の翻訳論
第5章 偽作経典の出現
第6章 翻訳と偽作のあいだ―経典を“編輯”する
第7章 漢訳が中国語にもたらしたもの
第8章 根源的だからこそ訳せないもの
第9章 仏典漢訳史の意義
著者等紹介
船山徹[フナヤマトオル]
1961年生。1988年京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退。現在、京都大学人文科学研究所教授。アメリカのプリンストン大学宗教学部、ハーヴァード大学神学部、オランダのライデン大学等において客員教授を歴任。中国中世仏教史とインド仏教知識論を中心に、仏教史を多角的に研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
デビっちん
31
サンスクリット語と言うインドの言葉が語源である仏典を漢語訳した過程を解説してくれています。どんな考えのもとどのような体制でどのくらいのスピードで漢訳されたかが詳細に綴られていました。その漢訳には「旧訳」と「新訳」があって、玄奘が新訳派の大家だそうです。三蔵法師は名翻訳家であり、語学の天才と言われる所以がわかりました。東アジア文化圏の文化を構成する漢訳という知的営みの世界がここにあります。2017/12/05
牛タン
6
仏典がどう漢訳されたか、歴史、訳者、翻訳にまつわる苦労等々。日本人が律を求めて隋唐に渡ったり、鑑真招聘を行ったのと同じように、漢人も律を求めて西域を越えて天竺へ知識を求めたのだなと。世界の中心地としての「中国」が仏教という思想の輸入を通して自らを「周辺地」として捉え直したという説が面白かった。偽経が作られた背景についてまとめた部分も面白かった。翻訳にまつわる苦労は言語や内容を越えて普遍的なものが多いなと思った2020/09/13
3000
6
「コンタクト・ゾーンの人文学」第一巻に掲載された論文を読んで以来、楽しみにしていた一冊。インド思想・仏教思想についてインド人の書く英語文献を読むようになり、簡単な単語程"読めていない"と感じることが多くなっていたのだが、本書を読むことで、その不安について理解を深めることができた。最近の原始仏教ブームを素朴すぎるように感じていた者としては、偽経・編集された経典の重要性について書かれた部分に膝を打つような気持ちになった。2014/05/02
in medio tutissimus ibis.
5
翻訳に伴う様々な困難を知るにつけ、しかしこれは漢訳にのみならず、本書が一括してインド語とした諸言語間の翻訳にも伴ったのではないかという気がする。少なくとも、サンスクリット化したのにかかわらず土着の言葉を一部残した仏教混交梵語はその所産だろう。金口に含まれた根源的ゆえに梵語へは翻訳しえないニュアンスが、仏教徒をして完全な梵語化を拒ませたに違いない。まさに無常な話だが、それ故に後世の仏教徒達は自らを救う仏説を時に創作せざるを得なかったのではないか。程度こそ違え擬典もまたその系譜に連なるものともいえよう。2022/04/30
暗頭明
5
あとがき冒頭にあるように概説という点において、私のような初学者には実に優れた良書だと言える。『高僧伝』(岩波文庫)の導きの書として今後、何度も繙くことになるのではないか。他方、たとえば目下、併読している『イスラーム哲学の原像』(井筒俊彦)がもたらす知的というにとどまらない興奮を引き起こしたり、『精神分析を語る』(藤山・松木・細澤)のややスノッブともいえる興味を掻き立てたりする要素が欠けると言える。せっかく専門家向けの専門書でない作品なのだから、もう少し著者の<思い>が熱く迸ってもよかったかなとも感じる。2014/02/09
-

- 電子書籍
- からん(7)