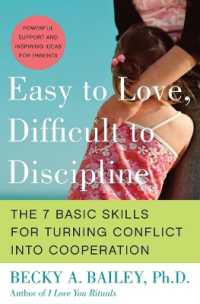出版社内容情報
「論壇」「文壇」とは何か。日本において「批評」はいかにして可能か。私たちは言論を支えてきたインフラやシステムの生成過程にさかのぼるところから再起動しなければならない。膨大な資料博捜に裏づけられた圧倒的な文体で知の基本構造をえぐり出す。思想界注目の新進批評家による、まったく新しいパースペクティブの誕生!
内容説明
「論壇」「文壇」とはなにか―。「批評」はいかにして可能か―。本書は日本の言論を支えてきたインフラやシステムの生成過程に立ちかえる試みである。論壇時評、文芸時評、座談会、人物批評、匿名批評など各種フォーマットの来歴の精緻な総括に批評再生のヒントを探る。膨大な資料群の博捜渉猟に裏づけられた圧倒的な文体が知の基本構造をえぐり出していく。論理と実証の融合による新しい思想のデザインへ。
目次
序章 編集批評論
第1章 論壇時評論
第2章 文芸時評論
第3章 座談会論
第4章 人物批評論
第5章 匿名批評論
終章 批評環境論
著者等紹介
大澤聡[オオサワサトシ]
1978年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員を経て、近畿大学文芸学部講師。専門はメディア史。各種媒体にジャーナリズムや文芸に関する批評・論文を発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
14
日本の批評環境がギルド的な職人世界から市場原理の世界へと大きく転換した1930年代の状況を、時評・座談会・匿名批評など、批評家個人ではなくメディアの在り方から研究した一冊。論の善し悪し以前に、情報収集の大変さがひしひしと伝わってきて(当時の新聞や雑誌を一つ一つ捲っていかないと書けない内容)、それだけでも読んだ甲斐があったと思った。現在当たり前になっていると同時に形骸化しているシステムのスタート地点をここに確認できる。全体から見えてくるのは、編集の批評的意味とネームヴァリューという呪いの逃れがたさ。2017/05/22
しゅん
12
7年ぶりの再読だったけど、こんな面白かったっけ?読者の拡大による経済圏の確立によって、文芸時評と座談会という形式、非専門家の批評家登用やメタ批評の発達という状況が1930年頃に偶発的に生み出される。形式は文芸誌で90年間延命し、メタ化や専門/非専門の溶解は反復される。環境としての批評の誕生を最短距離で探知していく文の流れ。単独の批評家として読まれている小林秀雄の批評方法も、メディア状況から生まれたものだという相対的な視点を提示している。論点のはっきりしない論争も、批評家のキャラ化も、昔からあったという話。2024/03/14
Nekono
8
戦前の「批評」について、多岐に渡ってシステムとして記述しようと試みている本。円本の流行とジャーナリズムの発達により限定読者から大衆読者へと広がった「本」への批評という行為と眼差しの変化をすくい取ろうとしている。その文体が凄まじい。/やー、体言止めを多用し、一つ一つの文が短い。じっくり読むための文体というより、疾走する文体だ。だから、最初は読みにくい。(私たち には閉口した。たち って誰だよ)しかし、慣れてくると読書が加速する。ちょっと気持ち良い。匿名の意味が変質した現代編も読んでみたい。2015/05/05
ころこ
6
単行本や全集などで、後進の我々が好き勝手に新たな解釈を試みる。その結果どの位売れどの位の読者にまず読まれたのか、どの様に読者に受け止められたのか。はたして後年、名高い批評文は掲載当時から同様に絶賛されていたのか。当時そこには同誌に掲載されているライバルがいて、表に出てこない編集者とともに、時には緊張関係にすらなります。さらに、読者のリテラシーと読者数(売上)と批評家との関係は、実は最も批評家のあり方を規定する要素です。書き下ろしでなければ、批評家の苦闘は雑誌や新聞に初出する現場にあるといえます。本書は、批2017/08/16
さえきかずひこ
5
第二章が面白かった‼︎「メディアはメッセージである」(マクルーハン)。2015/04/28