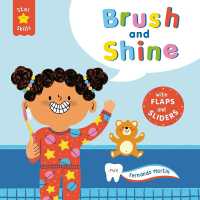出版社内容情報
「平成の大合併」によって,「村」という地名が消えようとしている.日本のムラは古代以来続いてきたので,これは歴史の大転換点である.古代の郷里制,中世の荘園制,近世の村落など制度上の仕組みとの関係に留意しながら,中世のムラを中心に,ムラの持続性とムラの生活を支えてきた「神々」について論じた画期的論集.
内容説明
平成の大合併によって、「村」という地名が消えようとしている。日本社会にとっては、大きな歴史の転換点ではないだろうか。古代以来連綿と続いてきた日本のムラ(自然に成立した村落共同体)の歴史を古代の郷里制、中世の荘園制、近世の村落など制度上の仕組みとの関係(国‐郡‐郷‐里)に留意して、その持続性や生活の諸相、さらにはムラを支えてきた「神々」について論じた画期的論集。併せて、ムラの歴史を明らかにする基礎作業として、ムラの戸籍簿をつくることを提言する。
目次
序章 ムラの歴史を考える―『香寺町史村の記憶地域編』のこと(『香寺町史村の記憶 地域編』の面白さ;『香寺町史村の記憶 地域編』の内容)
第1章 ムラの持続性について(風土記のムラ;古代伊豆のサトとムラ―今津報告にふれて ほか)
第2章 ムラの神さな(敷きます神)の発見(賀茂―日本の神と歴史学;村の神さま―山野河海理解における戸田的と網野的 ほか)
第3章 中世の在地社会を考える(荘園制;多様性としての列島一四世紀―網野学説をめぐって ほか)
終章 ムラの新たな研究のために―ムラの戸籍簿を作ろう(柳田国男『先祖の話』―ムラを忘れた歴史学;収集分類型分析ということ ほか)
著者等紹介
大山喬平[オオヤマキョウヘイ]
1933年京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科国史専攻博士課程単位取得退学。京都大学文学部教授、同文学部博物館館長、大谷大学教授などを経て、京都大学名誉教授。日本中世史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。