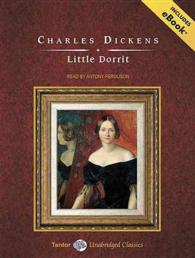内容説明
日本には漢詩愛好者が多いが、漢詩が最も輝いていた中国・唐代の人々は李白や杜甫の漢詩をどのような発音で詠んでいたのだろうか。四声や反切、韻書・韻図など中国音韻学の基礎的事項やカールグレン、マスペロなどの古代音研究の歩みを述べながら、その復元の方法をていねいに説き明かす。そして実際に唐代、長安生まれの詩人・杜牧「江南春」をどう詠んだかの復元を試みる。巻末に、当時の詠み方を試みた杜甫「春望」、李白「秋浦歌」、孟浩然「春暁」などの名詩10篇を付す。
目次
第1話 漢詩と韻―中国音韻学への第一歩(はじめに;漢詩と韻のはなし;古代中国語の音韻)
第2話 古代中国の音韻学―韻書と韻図をめぐって(中国の言語研究;“反切”のはなし―中国で生まれた表音法;「四声」のはなし―高低アクセント;韻書のはなし―韻引き字典;韻図―現代的な音節表)
第3話 古代音の実相に迫る―清朝の古代音研究(古代音の復元にむかって;古音研究の夜明け;古音研究の開花;中古音の探究)
第4話 古代音を復元する―杜牧「江南春」を唐代音で読む(近代的な古代音研究への旅立ち;“中古音”復元の方法)
著者等紹介
大島正二[オオシマショウジ]
1933年東京に生まれる。1963年東京大学大学院修士課程修了。専攻は言語学・中国語学。現在、北海道大学名誉教授・二松學舎大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
13
中国語の歴史的帰結を北京語で代表させるのは感覚的に合わない。京都弁が東京弁に歴史的に変化したと説明するに等しい。広東福建等南方語こそ文化的には近しく感じる。本書は唐長安の言葉で唐詩を復元する試みを通じて、中華音韻史を振り返る。中国言語学は古代から発展してきたが、専ら字義と字形に偏り、音韻は軽視されてきた。仏教伝来による悉曇学の興起と唐詩の流行が漸く発展を促す。更に清代に古音学として発展を遂げた。本書で日本朝鮮越南の漢字音が参照されるのも嬉しい。古くは有声無声の別が存在し、それが現代日本語に反映しているとは2024/09/17
夜吟秋月
3
紹介本。漢詩を製作しているので音韻学の変遷に興味を持てた。日本語でも数十年で変化するのだから況や中国など途方もなく変わっているであろう、どの時代もそうだがきちんと紙に記録しているのは優秀である。また、清代後期に中国に海外の学者から新たな考えがもたらされた点も他の学問の事例と共通していて個人的には楽しく読めた。2025/11/28
mcpekmaeda
2
漢字の形は太古の昔から変わらない。でも、発音は変化し続ける。それでは唐代の人はどの様に発音していたのだろうか?そんな疑問を解き明かすにはどうしたら良いのか。証拠となる様々な文献を示しながら、方法を分かりやすく説明している本です。でも時の流れの中、変わっていくものの元の姿を見つけるのは簡単ではないということも感じさせられます。 2024/02/06
W
2
国語関連の分野の中でも音韻学は全く興味の湧かない分野のひとつである。が、韻を踏むようになった背景を流し読みではあるが何となく知れて良かった。2018/06/01
うな坊
2
面白かった。でも音韻学って、難しそうな分野ですね。カールグレンというひとはすごすぎる。わずか20歳で基礎的な調査をおこない、25歳にならないうちに、中国音韻学に関する不朽の、かつ、巨大な研究を成し遂げたことに驚嘆するほかない。2011/06/03