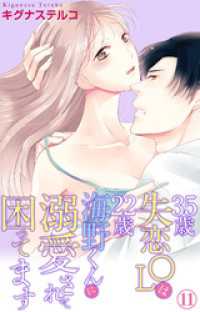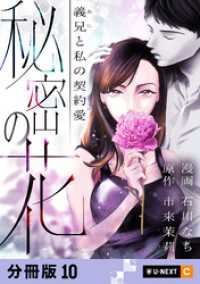内容説明
十四世紀に誕生した徒然草は、中世から近世へと移行する十七世紀において「再発見」され、爆発的流行の時期を迎える。変革の時代の中、人びとは新しい「古典」に何を見出そうとしたのか。漢学者・和学者たちの注釈書、古典講釈による庶民教化など、幅広い受容の様相をたどることで、近世文学の母体の一つとなった徒然草の姿を浮かび上がらせる。
目次
1 徒然草の位相―文芸と学問のあいだ(徒然草の「発見」―慶長文壇史の一齣;「つれづれ」の季節―十七世紀の時代思潮 ほか)
2 「情」と「理」のゆくえ―和学史再考にむけて(林羅山『野槌』論―中世歌学への挑戦;高田宗賢『徒然草大全』論―教誡主義からの離脱 ほか)
3 徒然草を「読む」「聞く」―古典講釈と庶民教化(徒然草講釈の技法―元禄‐享保期の指南書から;注釈と講釈―類版問題の余波 ほか)
4 注釈者たちの肖像(伊藤栄治―『鉄槌』編者説;南部草寿―明儒の風貌 ほか)
5 徒然草の波紋(徒然草から江戸文学へ―古典の転生;徒然草の図像学―近世初期の扇面と屏風 ほか)
著者等紹介
川平敏文[カワヒラトシフミ]
1969年福岡県生まれ。1999年九州大学大学院博士課程修了。博士(文学)。熊本県立大学准教授を経て、九州大学大学院准教授。近世文学・学芸史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。