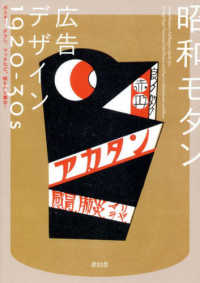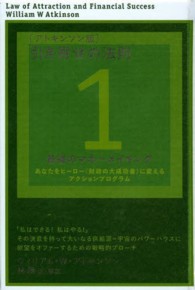出版社内容情報
古代社会に誕生した和歌は、なぜ時代を超えて生き続けることができたのか。古代和歌から中世和歌への飛躍こそが、文芸ジャンルとしての永続性を決定づけたのではないか。中世という時代において、和歌に何が起こったのか。歌人たちの創作の営みを通して、中世和歌の詩的達成を考究し続けてきた著者の長年の論考を集成する。
内容説明
古代社会に誕生した和歌は、なぜ時代を超えて生き続けることができたのか。古代和歌から中世和歌への飛躍こそが、文学としての永続性を決定づけたのではないか。中世という時代において、はたして和歌に何が起こったのか。歌人たちの創作の営みを通して、中世和歌の詩的達成を考究し続けてきた著者の長年の論考を集成する。
目次
第1編 古代和歌における中世―風景と主体(曽禰好忠の和歌表現;和泉式部の歌の方法 ほか)
第2編 中世和歌の方法的始発―縁語的思考と演技(源俊頼の方法と『俊頼髄脳』;西行の「ことばのよせ」 ほか)
第3編 中世和歌の形成―藤原俊成と藤原定家(千載集の羇旅歌;藤原俊成の縁語的思考 ほか)
第4編 中世和歌の展開―歌人と創作意識(源実朝と音;源実朝と『万葉集』 ほか)
本居宣長と『新古今集』―近世からの照射
著者等紹介
渡部泰明[ワタナベヤスアキ]
1957年生まれ。1981年東京大学文学部卒業。1986年東京大学大学院人文科学研究科国語国文学専門課程博士課程退学。フェリス女学院大学助教授、上智大学助教授を経て、東京大学大学院人文社会系研究科教授。和歌文学・日本中世文学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
akuragitatata