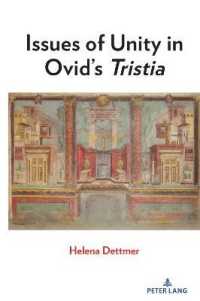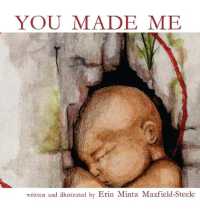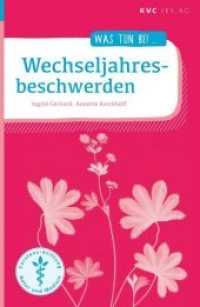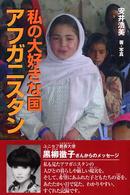出版社内容情報
疎外のない人間と社会の状態のヴィジョン-初期論考からの引用の束を自ら翻訳し、マルクスの感覚論と生活感覚を掘り起こす。ポジティブな全人的人間像と社会変革の思想との関係とは。人間性の解放に向けた思想の秘められた可能性を探って。
内容説明
マルクス、その可能性と限界―六〇年代、政治の季節の、こわばり青ざめた顔に血を通わせる、人間マルクスへの接近。著者自身の翻訳によって、死、性愛、感覚、音楽などをめぐる、初期マルクス・アンソロジーを編む。疎外のむこうにマルクスが見て取った全人的人間像を探り、その人間観・自然観の変奏のプロセスを追う。人間解放のヴィジョンの再生のために。
目次
序章 マルクスとわたし
第1章 ヘーゲルからマルクスへ―マルクスのヘーゲル批判
第2章 対自然・対人間―『経済学・哲学草稿』を読む1
第3章 全人的人間像―『経済学・哲学草稿』を読む2
第4章 社会変革に向かって―マルクスの人間観
終章 労働概念の変容
著者等紹介
長谷川宏[ハセガワヒロシ]
1940年生まれ。専攻は哲学。東京大学大学院博士課程単位取得退学後、大学アカデミズムを離れ、在野の哲学者として、多くの読書会・研究会を主宰する。また、41年間続く私塾・赤門塾は、ユニークな活動をもって知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さえきかずひこ
6
マルクスの労働観の変遷を通して、その思考のダイナミズムとスケールの大きさを分かりやすく示している入門書。ヘーゲルやフォイエルバッハからの影響についても簡潔に触れていて分かりやすい。2017/10/12
乱読家 護る会支持!
5
マルクスが打ち出した、共産主義国家という理想的な国家の概念。 しかし、それを継承したレーニンやスターリンといったマルクス主義者たちは、その理想社会を維持する国家のシステムを熟考するプロセスを経ずに、対資本主義との戦いに没頭していきました。 そして、共産主義国家として革命に成功した国々は、「共産党幹部の独裁」「国家による国民の弾圧」という、マルクスが目指した国家像とは全く真逆の国家を作ってしまいました。 そして、むしろ現在の日本の方が、よりマルクスの考えた共産主義の理想に近いようにも思えます。 2021/11/13
amanon
3
初期マルクスの思想をわかりやすく解説した良書。廣松を通してマルクスに接してきた者として、初期マルクスというのは、つい軽視しがちになるのだけれど、この時代のマルクスにも豊穣な思想をたたえていることを改めて認識。また、ヘーゲル哲学の強い影響下にありながら、それを乗り越えようとする若きマルクスの姿が感動的でさえあった。その一方でかつての教条的なマルクス理解や訳語の問題といったいわば負の側面にも言及しているのが興味深い。それから、マルクスの自然観という重要な概念を改めて認識したのも大きかった。マルクス入門に最適。2018/03/26
yo yoshimata
1
「ヘーゲル研究者がマルクスを読んだら、どんな感じになるんだろうか」と手に取った一冊ですが、読後感は、「初期マルクスだけでマルクスを語るのが無理があるな」という当たり前の感想。所々に共感できるところーーマルクスが五感すら、抽象的な「人間の本質」で考えず歴史的に捉えようとしていたことや、「宗教はアヘン」発言の解釈と未来社会への見通しーーはありました。2015/01/21
りんご飴
1
これはよい!@ 'ェ' @2014/06/30
-
- 洋書
- You Made Me