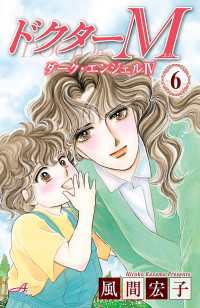- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
情報メディアはわれわれの生活に深く入り込み、人間関係や組織形態から価値観・感性までも変容させた。情報人類学はその変化し続ける人間の「現場」にこだわり、フィールド調査で新しい視点を提供してきた。本書は世界の多様な情報社会のありよう、人間と情報メディアの関係を比較分析し、近未来の情報社会を読み解いてゆく。
目次
第1章 情報人類学とは(情報人類学の研究領域;情報人類学の方法―フィールドノートから ほか)
第2章 情報とメディア―変容する定義と関係性(情報とは何か;メディアの発生)
第3章 情報社会論の系譜(工業社会の行き詰まりから生まれた情報社会論;「脱」した工業社会像を求めて ほか)
第4章 情報化による人間関係・家庭・社会の変容(「第三の社会」の浮上;「第三の社会」の概要 ほか)
第5章 情報コンテンツの時代―ジャパンクールの浸透と変容(「モノづくり」から「モノ語りづくり」へ;欧米で評価されたジャパンクール ほか)
著者等紹介
奥野卓司[オクノタクジ]
1950年京都市生まれ。関西学院大学大学院社会学研究科教授。学術博士。情報人類学・メディア表象論専攻。京都工芸繊維大学大学院修了。米国イリノイ大学人類学部客員准教授、甲南大学文学部教授などをへて、1997年から現職。2008年から国立国際日本文化研究センター客員教授を兼任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネクロス
4
図書館本。幅が広すぎて主題がぶれた感じがする。後半はアジアにおけるコンテンツ産業(主に漫画・アニメ)の流れについて。2014/03/03
えーてる
2
トフラーの予見した「第三の社会」がエレクトリック・コテージという移動しない社会であったことに対して、第三の社会はその関係性ゆえにより移動を頻繁に行う遊動社会になるだろう、というのが氏のたどり着いた結論だと思っていたけど、そこはさっさとスルーしてw、人類学の基礎であるフィールドワークにいそしんでいたのであった。80年代の「パソコン少年」をつぶさに観察した当時のレポートから、21世紀のアジアにおける「ジャパンクール」が浸透した現状までを無理矢理一冊にまとめた本。ちなみに本人の研究テーマはすでに別のところに行っ2009/11/05
kozawa
1
こういうジャンルで食って行けたら理想だなぁ。細部に違和感のある記述はたくさんあるし、主張・結論には同意しかねる点は多多あるが、その射程は興味深い、が著者はどこへ行くのだろう?2009/11/09
☆☆☆☆☆☆☆
0
大味な社会学的分析がほとんどで、「情報人類学」ってタイトルにはちょっと違和感を感じるかなぁ。あと「だが」がやたら多くて気になる。だがそれなりに面白かった。2012/08/09