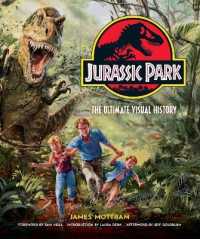出版社内容情報
十二名の古典研究者が、古典の深み、広がり、その豊かさを問い直す。現代人に贈る、沈思黙考のすすめ。
内容説明
古典とは何か、何の役に立つのか、古典はどうして古典なのか。人文学全般に向かい風が吹くなか、十二名の古典研究者が、古典の深み、広がり、その豊かさを問い直す。
目次
1 「古典」の意義について、考えてみました(中国における古典;古典とクラシック―ことばとことがら)
2 「古典」の成り立ちについて、考えてみました(ゲーテの「世界文学」とヨーロッパの「古典」;イギリス・ロマン主義時代の「古典」観;ドイツの夢―「国民」と「古典」;『源氏物語』はいかにして「古典」になったか)
3 「古典」の多様さについて、考えてみました(マニ教の「宇宙図」―東西交流のしるし;スラブ世界の古典語―言語の古層へ;古典演劇という幻想―生きて流動するもの;小学における「古典」―あらゆる学問の基礎)
著者等紹介
逸身喜一郎[イツミキイチロウ]
1946年生まれ。西洋古典学専攻。東京大学名誉教授
田邊玲子[タナベレイコ]
1955年生まれ。ドイツ文学・ジェンダー論専攻。京都大学大学院人間・環境学研究科教授
身崎壽[ミサキヒサシ]
1946年生まれ。日本古典文学専攻。北海道大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
32
古典は多くの書物のなかに交ざった一冊であるにもかかわらず、あるとき特別な意味をもってあるひとに立ち現れることがある(ⅸ頁)。古典には古典固有の、考慮すべき要因があることが見えてくる。ひとつは普遍性と個々の言語の関係という問題であり、もうひとつは規範と変わりゆく社会、歴史性の問題である(ⅻ頁)。規範は、①同時代の、これから書かれる書物の規範 ②よき生き方、知恵の規範 ③当該言語の規範 と異なった、ただし相互を排除することはない考え方(ⅹⅴ頁)。河合康三教授によると、清の乾隆帝による『四庫全書』の2018/09/22
虎哲
3
編著者の逸見は「古典とは何か」を考えた場合に①普遍性と個々の言語の関係という問題②規範と変わりゆく社会、言わば歴史性の問題の2つの古典固有の、考慮すべき要因があると主張する。(16頁)この2つの問題は本書で度々扱われており、貫く重要なテーマの1つだと言える。「ナショナリズム」と結びつく古典というのが特にどの国にも見られた。「Ⅲ「古典」の多様さについて、考えてみました」は今の私には力がなく分からなかった。身﨑による「おわりに-古典教材談義」は示唆に富んでおり、改めて今後私が当たるべき本や論文が明確になった。2019/02/20
良さん
2
「何のために学ぶのか」古典を話題にしているが、学問の意義・目的は、広く人文学全体が、いや人類全体がもう一度取り組むべき問題ではないか。私は古典や源氏物語が専門だから、そこから考えていきたいと思う。 【心に残った言葉】急いで答を出そうとしないで、まずはじっくり考えてみよう。(オビ)2016/12/10
夏みかん
2
良くも悪くも「研究者が書いた本」って感じでした。話題がいっぱいあって面白いのですが、まとまりにかけます。一般人がイメージする古典の話題とはちょっと違います。でも、私には面白かったです。特に「古典」という言葉そのものの定義や出典のこだわりとか、古典演劇にまつわる話とかはとても興味深かったです。世界と日本との違いとか関わり方とか「歴史」にも通じる問題だと思いました。2016/11/15
-
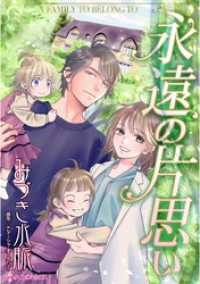
- 電子書籍
- 永遠の片思い【分冊】 1巻 ハーレクイ…
-
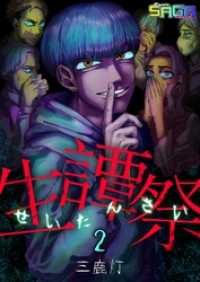
- 電子書籍
- 生譚祭 2 Comic SAGA