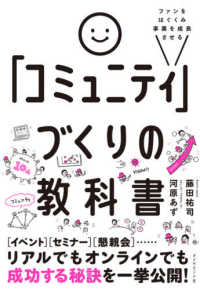内容説明
一九九〇年代、米国では児童虐待認知件数が激減した。子どもと女性の暴力被害研究の世界的第一人者フィンケルホーは、さまざまな研究資料をもとに、虐待発生件数の激減は事実であると立証した。なぜ減ったのか。そして減らすためにはどんな施策が必要なのか。個別の被害ではなく総合的に被害を把握すること、そして被害の影響の発達に応じた違いを検証する方法、などを掲げた「発達被害者学」(子ども被害者学)を提唱する著者からの提言。
目次
1章 子どもの被害(「子どもは最も被害に遭っている」についての論争;新しいタイプの犯罪 ほか)
2章 発達被害者学(定義と分類の問題;子どもの被害の広がり ほか)
3章 危険に曝される子ども(何が子どもを危険に曝すのか;多重被害への道すじ ほか)
4章 発達上の影響(子ども時代のトラウマという分野;被害の衝撃的作用に関するさらに一般的なモデルを目指して ほか)
5章 朗報 子どもの被害は減っている―だが、なぜ?(実際に改善しているのか;幅広くさまざまな減少 ほか)
著者等紹介
森田ゆり[モリタユリ]
エンパワメント・センター主宰。立命館大学客員教授。80年代初頭より日米で子ども・女性への暴力防止専門職の養成に携わる。90年代はカリフォルニア大学で主任アナリストを務める。88年に朝日ジャーナル・ノンフィクション大賞、98年に産経児童出版文化賞、2005年に保健文化賞をそれぞれ受賞
金田ユリ子[カネダユリコ]
1965年生まれ。88年東京都立大学人文学部卒業。武蔵野大学心理臨床センター研究員
定政由里子[サダマサユリコ]
1977年生まれ。臨床心理士、甲南大学人間科学研究所リサーチアシスタント
森年恵[モリトシエ]
ブリストル大学大学院で女性学、レディング大学大学院で映画学の修士号取得。甲南大学文学部非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てくてく
takao
たらこ
にしき よう
morikawa