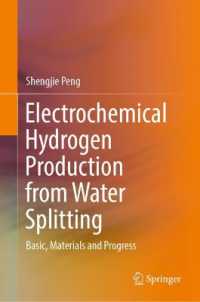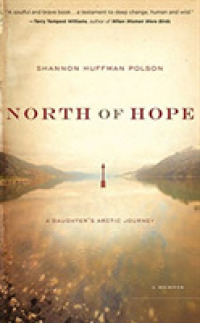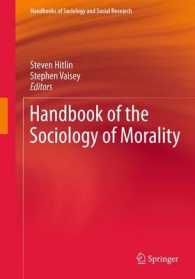内容説明
多くの子どもたちが親しんでいるゲームやネットなどの仮想世界は、子どもたちの心にどのような影響を及ぼすのか。私たち大人は、子どもたちに仮想世界とのつき合い方をどう教え、仮想と現実の二つの世界の接点をどのようにつくりだしていけばよいのか。一九七〇年代末から小学校でのコンピュータ教育を実践してきた日本のパイオニア教師としての経験と、最新の脳科学の成果にもとづいて、幼い子をもつ親や教育関係者の不安・疑問に答える「未来への処方箋」。
目次
第1章 教室の中のキッズ・ウォー(仮想と現実の汽水域;ちびデジタル子ちゃんとアナログしんちゃん ほか)
第2章 バーチャル世界の影(宇宙服の少年と暗闇から来た少女の物語;脳の「五つの窓」 ほか)
第3章 春の鏡と夏への鋏(ごんぎつねと子ども脳;子ども脳の「春の鏡」 ほか)
第4章 小さなモーツァルト、幼いロボット工学者(祐子ちゃんのふしぎな質問;エリちゃんと仮想の「かめさん」 ほか)
第5章 桶の中の脳っ子のブルース(桶の中の脳っ子の憂鬱;世界へ歩み出す「窓」と絶滅から救う「船」)
著者等紹介
戸塚滝登[トツカタキト]
1952年、富山県生まれ。富山大学理学部物理学科卒。1978年から2003年まで、富山県内の公立小学校で教諭を務める。70年代末よりコンピュータ教育を実践。日本のコンピュータ教育のパイオニアの一人。現在は、子どものための教育ソフトウェアの研究開発と、ネットモラルの教育に従事。作家、早稲田大学こどもメディア研究所客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
G-dark
かねかね
oko
いわたん
のうみそしる