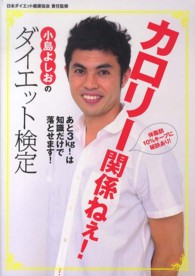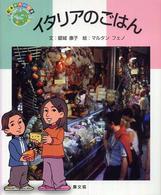内容説明
フランスが革命へと向かう、激動の一八世紀。それは、子どもをとりまく社会環境もまた、大きな変貌を遂げた時代であった。教会、王権、そして革命政府は、学校教育をいかに構想したのであろうか。子どもに向けられる大人たちの視線は、どのように変化したのであろうか。農村教師の日記や、当時好評を博した子ども向け雑誌『子どもの友』、革命期に創られた「愛国少年」の伝説など、興味深い史料を読み解きながら、子ども/家庭/学校をめぐる一八世紀フランスの社会文化史を描く。
目次
第1章 すべての子どもを学校へ―初等教育の組織化(アンシャン・レジーム期の初等教育政策;初等教育の広がり―一八世紀末の状況 ほか)
第2章 国家を担う人材の育成―エリート教育の改革(高等法院のコレージュ改革;「有能な軍人」の育成をめざして)
第3章 家庭から学校へ―「近代家族」の子育て(家庭の中の親と子―『子どもの友』の世界;管理される教育に向かって―寄宿生の増加)
第4章 「良い子」の誕生―子ども像の変遷(「狡猾」から「純真」へ―子ども向け読み物の中の子ども像;「英雄」になった子ども―フランス革命期の愛国少年伝説)
著者等紹介
天野知恵子[アマノチエコ]
1955年生。愛知県立大学外国語学部教授。フランス近世近代史、フランス革命史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
13
元々カトリック教会が、プロテスタント排撃のために、各教区に「小さな学校」を立てる。そこの教師は、教育だけでなく、司祭の補佐役にもなる。革命が全てを変える。カトリック系教師は首になり、「共和国精神」を子供に教える教師が送り込まれる。しかし国家が給料を払えなくなり、カトリック私立学校にも教育の権利を認める。公立教員は生徒から授業料を直接徴収することになり、私立と公立の競争へ。高等教育は、イエズス会系コレージュ(四分の三)でラテン語教育。寄宿学校が増えるが、寄宿料は高額だったから、そこは良家の師弟に限定される。2021/02/27
シルク
10
なんか定期的に読みたくなる本。どの章が読みたいとか、どの箇所が読みたいとか、そういうのでは多分ないのだな。わたくしはまず、この本のこの表紙絵が大好きなのだ。身なりの良い少年が、机に向かってる。勉強机やんな、それ? って感じなのだけど、本やらの勉強道具はズザザー、と脇にのけられちゃって、彼の前にはくるくると回るちっちゃな独楽♪ それを見つめる少年の、なんとも満たされたこの表情を見よ! ての。この表紙が見たくて、この本を繰り返し手に取る。この絵が、わたくしにとって、大きな喜びであるのだ。 2018/06/27
こぐ
1
教育論とかではないです。フランス革命期、ジャコバンのプロパガンダに子供が使われるとか、そういうのは納得。それよりも学校の普及の背景にあった社会情勢が面白かった。2008/10/12