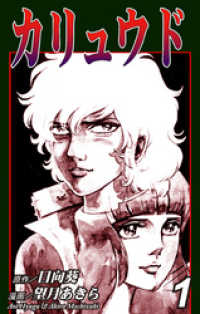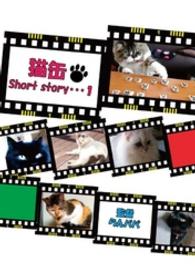内容説明
「旋律の引用論」の提起から、東洋音楽が持つ「見えない音楽理論」の発見へ。やがてアジアの民族音楽の保存と継承に関わる中から、民族音楽活性化の理論として「フィールドバック」の概念を提起する―音楽の生まれる現場に注目してきた著者が常に考えてきたのは、人間にとって音楽とはなにか、という問いである。理論と現場の間で思考を展開してきたユニークな音楽学者の、生涯をかけた渾身の労作。
目次
最終講義―音の動きの分析から、社会的脈絡における音楽の研究へ
第1部 音楽とはなにか―音の分析から音楽記号学へ(情報理論からみた音楽;三味線音楽における引用;モーツァルトと間テクスト性;音楽記号学とアジア・日本音楽)
第2部 見えない音楽理論―日本音楽にひそむ構造(日本伝統の音とは(平野健次氏と共著)
見えない理論―音楽の理論・楽器・身体(蒲生郷昭氏と共著)
表象としての日本音楽)
第3部 フィールドから考える―民族音楽学へ(民族音楽学再構築と自分の歴史;比較音楽学から民族音楽学へ;ミャンマー ヤンゴンとマンダレーの古典音楽―器の音、そして声(山口修氏と共著)
開発と音楽文化のゆくえ
生きた伝統としての音楽活動の支援
音楽・テクスト・コンテクスト)
著者等紹介
徳丸吉彦[トクマルヨシヒコ]
1936年東京生まれ。東京大学文学部・同大学院修士課程にて音楽学・美学を学ぶ。1982年にカナダのラヴァール大学より、『三味線音楽の旋律的様相』で博士号を取得。国立音楽大学、お茶の水女子大学(途中でモントリオール大学客員教授、カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員教授)、放送大学での勤務を経て、聖徳大学教授、放送大学客員教授、お茶の水女子大学名誉教授。音楽学(とくに音楽記号学と民族音楽学)と芸術文化政策を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nagao.shiraz
BsBs


![ストーカーを撃退してくれた憧れの人は、もっとヤバいストーカーだった[ばら売り] - 第24話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1981557.jpg)