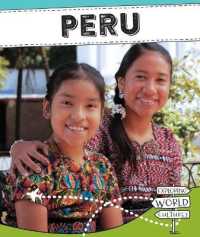内容説明
脱俗・孤高の精神の台所。橘曙覧、契沖、鴨長明、西行、本居宣長…さまざまな“なりわい”と性の形を見つめ、文学が生成する場所、無用者の回廊をめぐる。
目次
外に居る者
町人の血
もののふのつら
聡明を濫用せず
親類の義理
歌を売る
賤の夫
飯料
「憂事」と「虚貝」
我を知るひと
遁世さまざま
うらめしの世
遁世造型
二重の遁世
著者等紹介
富岡多惠子[トミオカタエコ]
詩人・作家・批評家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あ げ こ
10
知れば知るほど掴み難くなる類のもの。隠者、隠士。しかし、俗臭を厭い、遁世したもの達の、俗世との接触、言わばその俗臭の痕跡を求める道筋で出会った彼等の姿には、身遠さより不思議と近しさを、届かぬ偉人に抱くそれとは別の、馴染み深い好悪の感情を覚える。特に好ましく感じたのは橘曙覧。その無邪気さ、時に迷惑でさえあるのに、あまりにも率直で、無邪気過ぎるが故に、反感を抱かれにくく、かえって好感を持たれるタイプのそれ…援助者の存在が必要不可欠な隠者生活において、才と共に武器となり得る魅力の一つだったのではないかと想像。2015/09/08
AR読書記録
4
比較的軽い書きぶりで、まあ随想というべきかとは思うけれど、十分に学術的な方面からも取り入れられるべきじゃないかという知見が随所に見える。「隠者」ということ、俗世のしがらみや執着をすっぱり断ち切る孤高の精神、という印象をもつけれど、そうはいっても人間食わねば生きていけない、というところから、実際どう世間とつながっていたか、またそのことに「隠者」の側もどのように感じるところがあったかを、丁寧に追う。折口信夫なんかは、全然そういう背景は知らなかったからなぁ。ふむぅ。ところで表紙の「性の形」って、「さが」かね。2016/12/15
舟江
3
橘曙覧を調べるために読んだ、他の本は思想を中心に書かれているが、この本は「生活」の部分も書かれており、当時の習慣なども解りやすく書かれている。2017/04/28
-
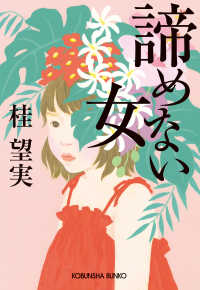
- 電子書籍
- 諦めない女 光文社文庫