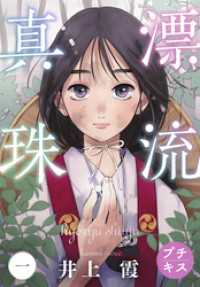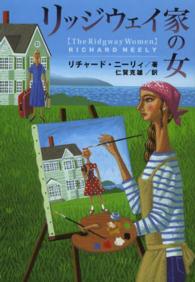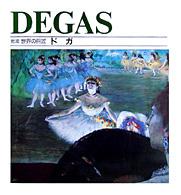内容説明
国家安全保障は今や終焉の時を迎えつつある。新たな脅威の下で、いかなる構想が求められているのか。本書はベンサムによる個人の安全保障の時代から、軍事力による国家安全保障を経て、現在模索されている平和と共生に基づく安全保障に至る二〇〇年の理念の変遷を鮮やかに解明する。二一世紀の今を斬新な角度から照らし出す著者渾身の書き下ろし。
目次
第1章 「安全保障」の系譜(訳語としての「安全保障」;「セキュリティ」の多様性 ほか)
第2章 憲法の最高価値としての安全保障(自然法論と法実証主義、功利主義;ベンサムの『永遠平和綱領』 ほか)
第3章 国家安全保障という体制(国家安全保障への途;甲殻類国家の誕生―国家安全保障法(NSA)の設置 ほか)
第4章 動き始めた新たな安全保障構想(安全保障構想;「人間の安全保障」と軍事力 ほか)
第5章 今後への展望
著者等紹介
古関彰一[コセキショウイチ]
1943年東京都生まれ。早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了。和光大学教授を経て、1991年より獨協大学法学部教授。専攻=憲政史。日本国憲法の制定過程に関する研究、憲法の平和主義の軌跡を講和条約、安保条約との関わりで解明する仕事をしてきた。この十余年、安全保障に関する提言や歴史的変遷を新たな視角から考察している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
23
人間の安全保障(HS)は、個人中心、人間中心の安全保障へと移行してきたことがわかる(7頁)。近代の始まりにあって、安保は国内の基本法、個人が保障される最大の人権(傍点、16頁)。マルクスは『ユダヤ人問題によせて』(1844年)のなかで、フランス革命期の憲法について、安全(傍点)は市民社会の最高の社会概念で、利己主義の保障(20頁)としているようだ。安保securityと安全safetyの線引きは困難だと著者は考える(23頁)。人権は国民権に変質してしまったという(39頁)。 2014/09/17
電球
2
本書では「security」を単に「国家安全保障」の意味で定義付けて論ずるのではなく、社会保障やSSRや人間の安全保障など「security」が名詞としてつく多くの分野について包括的に論じており、改めて「security」という言葉を模索する上でのゲートウェイを担う一冊となる。また、著者は「security」に関して主に理論の面で論じ、その引用も多数あるのでsecurityを理論面で学ぶ上でも大きな役に立つだろう。私個人としては、「security」の持つ役割の変遷に関して論じている点が興味深かった。2014/01/02
sayan
1
戻りの飛行機もやっぱりAPECの影響でとんでもない遅延。今回の出張で持っていた書籍数が少なかったなと思うほど・・・。p.174国家安全保障は、終局的な基準として「主権」を持っており、社会的安全保障は「アイデンティティ」を持っている。双方の用語法は生き残りを意味する→アイデンティティを失った社会は自らもはや生きていけない恐怖を感ずる→ウィーバーの中心概念(ハンガリーPual Roeの論文を参照)p.175社会に対する脅威を通じて国家がinsecurityになる→土佐弘之、バリーブザンの論文を再読して要分析。2015/11/18
sayan
1
2章と4章を中心に読了。特に、問題意識として持っているカントとベンサムに関して。p.61ベンサムは、人々の期待あるいは安全の保障を重視したが、それは権利の保障自体が重要だからではなく、期待と安全の保障が社会の福祉の最大化につながるからである。p.77カントは安全保障に決して言及しなかったが、「平和」の問題として提起した「友好」は、「難民問題」として、安全保障の柱の一つになっている。p.78カントとベンサムは、それぞれ、国際的視点から、国内的視点から平和と捉えている。4章で、特に人間安全保障は別でまとめる。2015/10/25
sayan
1
セキュリティの多様性:ホッブスとスミス、そしてベンサム(p.12-17)近代国家の安全保障(p.25-33)個人保障から社会保障へ(p.34-40)憲法の最高価値としての安全保障(p.55-88) →憲法とは何か、の長谷部先生の書籍と共通する部分(ルソー:戦争は相手国の憲法:安全保障(観?)を書き換える事が目的部分)動きは始めた新たな安全保障構想(p.143-202)社会的安全保障、p.76-772014/06/26