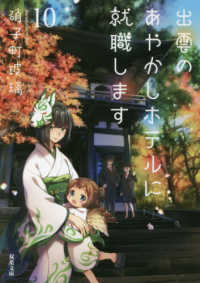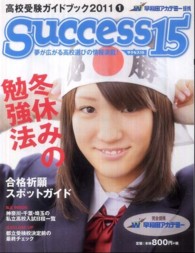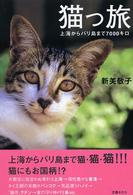出版社内容情報
近代においてセクシュアリティは,「語りえぬもの」とされてきた.そのタブーの源泉を見極めずに,抑圧的な規範を崩すことはできない.もっとも個人的とされる事柄のうちに潜む政治性を,気鋭の理論家が論じきった注目の書.
内容説明
わたしたちは何らかの物語なしに、「女」や「男」として感じることも、行動することも、理解することもできない。だが物語はいつも比喩であり、その比喩が事実として作用する。それではわたしたちの感情やふるまいは、どんな物語から来ているのか?本書はセクシュアリティの力学から照射して、親密性の領域として近代社会の深奥に秘匿されてきた事柄をめぐって、繰り広げられてきた思考の軌跡である。個人的なものの追求は、個人を規定し、個人を自他共に説明している関係性の網目を穿ち、そのすきまを押し広げて、これまで語りえなかったものに声を与えることである。“わたし”へのたえまない問いかけのなかで、アイデンティティと欲望の相互交差を解きほぐし、「政治」「倫理」「正義」「狂気」を未来に向けての新しい舞台のなかに位置づける困難な作業を、気鋭の理論家が渾身でとりくんだ注目の書。
目次
序 「愛」について「語る」ということ
第1章 “ヘテロ”セクシズムの系譜―近代社会とセクシュアリティ
第2章 愛について―エロスの不可能性
第3章 あなたを忘れない―性の制度の脱‐再生産
第4章 アイデンティティの倫理―差異と平等の政治的パラドックスのなかで
第5章 “普遍”ではなく“正義”を―翻訳の残余が求めるもの
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
;
7
すごく良かったけれど、5章の表象不可能性の議論がかなり危うく感じた(結局批判していたはずのクリステヴァの立場と変わらなくなってしまうのでは、と思った)のであとで全体を再読、検討したい。2019/07/20
ヒナコ
5
表題にもなっている第2章「愛について」の部分について言及しておきたい。 言語的存在である人間にとって愛の欲望の成就がそもそも不可能でことを基に、なぜ精神分析が愛を語る時、「正常な」愛を詳しく語らずに、「病理的な」愛を詳しく語ってしまうのかを竹村は問題にする。竹村は「正常な」エロスを語ることを精神分析家が都合よく忘れていると精神分析の文法に従って指摘するのであるが、実は精神分析の政治的無意識こそが、エロスの可能性を抑圧していると告発する。 手品のような精神分析のフェミニスト的書き換えは一読の価値あり。2016/08/10
yanagihara hiroki
3
第三章が確かに白眉だが、第四章も第五章も本当に素晴らしい。もちろんフェミニズムの本として仮借ない洞察を与えてくれるとともに、その射程には収まらずに我々の様々な「多数派」的暴力へと分裂を与えてくれる。正義の申立ては「狂気」であるが故に正しいのなら、この本における、我々の依拠する社会的・認識的構造への透徹した竹村の探究は、正に「狂気」の産物であり、それ故に耳を傾けずにはいられない。有名な言葉を借用すれば、「高度に発達した研究は、もはや思想と見分けがつかない」ということの好例であり、必読の本だと思う。2022/03/11
S
2
以前読んだ竹村和子によるフェミニズム入門書に当然のようにポストコロニアリズムまで書かれていて、当時フェミニズム自体にあまり明るくなかったのもありそれが不思議だったが、この本を通して全体のつながりがなんとなく分かった。ただ理解したような気がする事柄を自分の言葉で語り直そうとするとつまってしまう。既存の言語に則らない事柄を語ろうとする者のこと、その語りのこと、その語りとのずれ、主体になること。差異を際立たせる「共通性」に対しての「普遍」についての部分が特に面白かったし希望っぽくもあった。2023/09/17
笠
1
大文字の〈女〉ではないメリル・ストリープ (『マディソン郡の橋』評より) 次は竹村の映画批評を読みたい エロスの不可能を論じた2章と母娘の関係を論じた3章が特に白眉だけど時代遅れ感も否めないのかもしれない それに比して4章5章は現代においてもアクチュアルな論考であるように思った2023/03/05
-

- 和書
- 有機量子化学