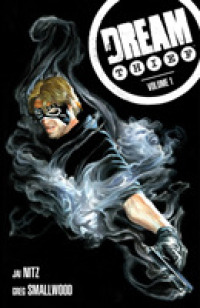出版社内容情報
一一世紀以降、ユーラシア大陸西部では、統治や宗教のあり方の変容、都市社会の発展、官僚制の整備などにより、いかなる種類・形態の「国家」が立ち上がったのか。また境域イベリア半島やアナトリアをはじめとする各地域の内部では、どのような過程で文化混交が進んだのか。トランスカルチュラルに流動する中世社会の実像を描く。
内容説明
一一世紀以降、ユーラシア大陸西部では、統治や宗教のあり方の変容、都市社会の発展、官僚制の整備などにより、いかなる種類・形態の「国家」が立ち上がったのか。また越域イベリア半島やアナトリアをはじめとする各地域の内部では、どのような過程で文化混交が進んだのか。トランスカルチュラルに流動し変成する中世社会の実像に迫る。
目次
展望(中世ヨーロッパ・西アジアの国家形成と文化変容)
問題群(中世ブリテンにおける魚眼的グローバル・ヒストリー論;帝国領チェコにみる中世「民族」の形成と変容;西アジアの軍人奴隷政権)
焦点(異文化の交差点としての北欧;レコンキスタの実像―征服後の都市空間にみる文化的融合;宗教寄進のストラテジー―ワクフの比較研究;「女性の医学」―西洋中世の身体とジェンダーを読み解く;イスラーム支配下のコプト教会;中世のユダヤ人―ともに生きるとは
著者等紹介
大黒俊二[オオグロシュンジ]
1953年生。大阪市立大学名誉教授。イタリア中世史
林佳世子[ハヤシカヨコ]
1958年生。東京外国語大学学長。西アジア社会史・オスマン朝史
鶴島博和[ツルシマヒロカズ]
1952年生。熊本大学名誉教授。西洋中世史
藤井真生[フジイマサオ]
1973年生。静岡大学人文社会科学部教授。中世チェコ史
五十嵐大介[イガラシダイスケ]
1973年生。早稲田大学文学学術院教授。中世アラブ・イスラーム史。マムルーク朝史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
MUNEKAZ
ポルターガイスト