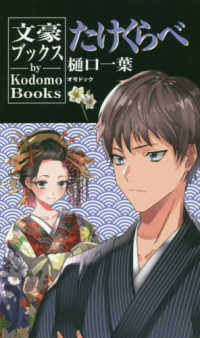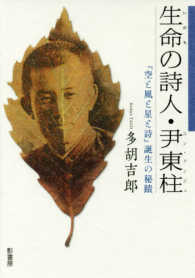出版社内容情報
一八五九年の開港によって「パックス・ブリタニカ」という自由な世界経済に組み込まれた日本。近世に胎動した成長をベースに、先進諸国の技術や制度を導入した明治の日本社会が「産業革命」を成し遂げていく過程を示す。
内容説明
市場の統合と分業の深化による「アダム・スミス的成長」を経験し、1人あたり国内総生産(GDP)が欧州でもっとも貧しかった諸国と並んだ19世紀半ば、1859年日本は開港した。第一のグローバル化時代、統合された自由な国際市場に組み込まれながらも、「スミス的成長」の基礎の上に、欧米先進諸国の技術や制度を積極的に導入した明治の日本社会は、非欧米諸国で初めて「産業革命」を体現する。その過程を新推定の各種経済指標を用いて明らかにする。
目次
序章
第1章 労働と人口 移動の自由と技能の形成
第2章 金融 近代的金融システムの形成と企業金融
第3章 農業と土地用益 明治の農業と都市不動産業
第4章 鉱工業 産業革命期の鉱工業
第5章 商業とサービス 交通革命と明治の商業
巻末付録 生産・物価・所得の推定
著者等紹介
深尾京司[フカオキョウジ]
1956年生まれ。一橋大学経済研究所教授。研究分野:マクロ経済学、国際経済学、経済史
中村尚史[ナカムラナオフミ]
1966年生まれ。東京大学社会科学研究所教授。研究分野:日本経済史、日本経営史、鉄道史、地域経済史
中林真幸[ナカバヤシマサキ]
1969年生まれ。東京大学社会科学研究所教授。研究分野:経済史、経営史、取引システム、比較制度分析(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
cochou
-

- 電子書籍
- 奇妙な家庭教師 2【分冊】 9巻 ハー…