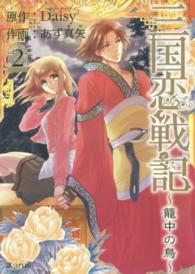内容説明
価値観が多元化した社会で感じる閉塞感。気遺いに満ちた「優しい人間関係」のなかで圏外化におびえる恐怖感。ケータイやネット、家庭から学校といった日常は、過剰な関係依存と排除で成り立っている。子どもたちにとって、現実を生き抜くための羅針盤、自己の拠り所である「キャラ」。この言葉をキーワードに現代社会の光と影を読み解き、「不気味な自分」と向きあうための処方箋を示す。
目次
第1章 コミュニケーション偏重の時代(格差化する人間関係のなかで;コミュニケーション至上主義)
第2章 アイデンティティからキャラへ(外キャラという対人関係の技法;内キャラという絶対的な拠り所)
第3章 キャラ社会のセキュリティ感覚(子どもと相似化する大人の世界;子どもをキャラ化する大人たち)
第4章 キャラ化した子どもたちの行方
著者等紹介
土井隆義[ドイタカヨシ]
1960年生まれ。筑波大学大学院人文社会科学研究科教授。専攻は社会学。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程中退(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
38
子どもたちの自己肯定感の低さは、日本社会の大きな社会問題といえる。そして、自らをキャラ化することでコミュニティでの存在感を得ようとすることは、そのキャラを演じられなくなったとき、コニュニティに居場所はなくなっていく。それは一つの排除型社会の側面である。寛容さを見失っている日本社会において、キャラ化を一つのキーワードとして論じる視点は大いに納得できるものであった。2020/06/12
Shoji
28
加害者は言う「被害者は誰でも良かった」。大変残念であるが、良く聞くパターンだ。そんな犯罪者の像をモチーフにして、ネット社会に生きる若者の心性や人間像を著者なりに述べています。かなり、深刻な内容だと思った。ネット環境が普及し、あえて不都合な他者と出会わなくても生きていけるようになった便利な時代。異種混合の人間関係に対する耐性力を養わなければならないそうだ。一体、ネットとはコミュニケーションが便利なのか、不便なのか、どちらなんだろう。考えさせられた。2024/01/18
suite
23
第三章の親子関係、教員と生徒の関係、教員と親の関係のあたりの考察、なるほどな…というところ。とにかく、相手が誰であれ、健全な関係を保っていくには、健やかな自己肯定感が必要で、そのためには、他者との関わりを恐れず、様々な人と胸襟開いてつきあい、そして、どんな自分も受け入れること、そして、過去へ過去へ遡っていくのでなく、先を見ていこう…というところ、かな。こちらを読みながら、先日読んだアドラーさんを思い出した。2016/02/12
小鈴
16
2009年出版。「キャラ」という用語は既に定着し日常用語にすらなっているが、ここで書かれた分析はまったく古びてないだろう。今の子どものとりまく環境は今もたいして変わっていないため必読書といえる。第四章「キャラ化した子どもたちの行方」は閉塞化するコミュニケーション/キャラ化した自己が傷ついたとき/「確固たる自信のなさ」の蔓延/「不気味な自分」と向き合う力について。大きな物語を喪失した時代は多様で相対的な価値観しかないがゆえにキャラを設定するということが人間関係の技法として定着した。不安定で不透明な2024/09/14
センケイ (線形)
14
複数の人格や、それを演じている側面について、悲観寄りに詳説した冊子。分人化に関心があったため、より実感のわくようなたとえとともにそのようなアイデンティティーの持ち方について動機が説明されるのはありがたいところ。また、親との関係や学校に寄せられる期待の変化など、周辺状況との関連についても説明がある。最後に示される提案は、広い意味で人の変化の可能性に期待するもので、自分の考えにも近く、また若干だが希望を感じるものだった。2020/09/30