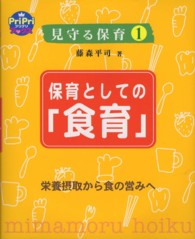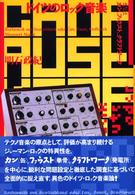出版社内容情報
紛争当事者の心が通じ合えば,平和への確かな一歩が築かれる.創造性に満ちたアイデアを提示するためには,私たちは日常生活の場で発想をどう転換していくべきだろうか.平和学の第一人者による「目からウロコ」の平和論.
目次
紛争を平和的に転換する
「和解」のために何が必要か
異なる文化を理解する
平和の経済へ
「9・11事件」を考える―平和報道への期待を込めて
イラクとアメリカの対話について
著者等紹介
ガルトゥング,ヨハン[ガルトゥング,ヨハン][Galtung,Johan]
1930年、ノルウェー生まれ。国際NGO「TRANSCEND」共同代表。59年、オスロ国際平和研究所を創設。「構造的暴力」の概念を軸にした平和学の研究者であり実践者である。世界各地の大学で平和学関係の客員教授。国連機関を中心に国際紛争解決に向けたコンサルタントの仕事も多い
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
33
初読。2014年98冊め。たいへん興味深い一冊。個人レベルでもこの考え方を日常的に自分のものにできれば生活がかわるだろう。フセインとブッシュが討論をしたらという頁もおもしろい。2014/02/15
白義
9
平和学の第一人者、ガルトゥングの市民講演を書籍化したものだが、あくまで平和への道筋をつけるための思考モデルの紹介にとどまっていて、その分析の一つ一つも図式的で浅いので期待すべき点を間違えるとつまらない可能性が高い。分析、検証、謝罪と許しといった扮装から和解への手法を手短にまとめているのは分かりやすい。また、平和構築のための経済、報道といった視点もある。門外漢への入門、説得という要素は希薄で、最初から本格的な著書に挑んだ方がいいが、すぐに読めたのでよかった2014/05/22
なおこっか
4
紛争調停のコンサルティングもしていたガルトゥング氏による平和を創る発想術講演録。今すぐ砲撃を止めるための解決策ではないが、長い目で見た時に世界の人々が認識しておくべき内容。曰く、戦争、紛争に関わった両者が共に復興に関われること。勿論、加害者と被害者を痛み分けするという意ではなく、加害者も然るべき償いの上で、その後も社会に関わり続けられるようにする。ジャック・アタリとイアン・ブレマーが異口同音にロシアを知るべきと語っていた事と通底する。また、戦争を経済に結びつけさせないこと。この点が今、線が引けていない。2022/04/08
1.3manen
2
ホーポノポノとは、ポリネシア語で「曲がったものをまっすぐに直す」(17ページ)ということば。地域でのトラブル、人間関係の修復法らしい。評者は長年、自営業との諍いで健康を害し、人権侵害に遭ってきた。本著から見えるのは、個人レベルのトラブルから、国家間の戦争に至るまで、結局は、人間と人間の不信感から悲劇に至っている状況を、どう修復するか、という点が共通している。一旦、崩れた人間を修復することは容易でないし、世代間で憎しみの継承が起こってしまう。修復学、という学問が許されるならば、信頼回復の道筋を解明するのだ。2012/07/28
0_felicitas
1
対話を中心とする問題解決のあり方は非常に大切だと思う。対話の場を持つためには仲立ちが必要なこともある。その場合は相手が暴力を向けない第三者をよく探すことに焦点を当てるべきだろう。2013/04/30