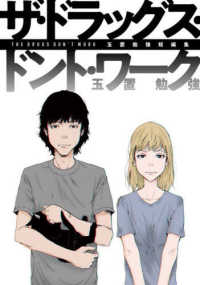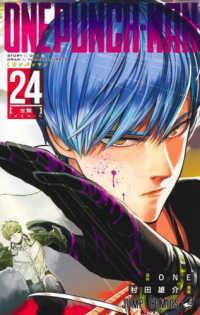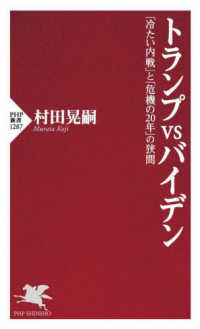内容説明
『幾何学に王道なし』はユークリッドの名言として知られている。それ以上に永久不滅なのは、命題・定理・証明という今日の数学書のスタイルを決定づけた著書『原論』である。本書のあまりに無駄のない記述が逆に多くの謎を生み古今の多くの論争を引き起こしている。ユークリッドその人もまた謎である。いったい誰に向かって何を書こうとしたのか。原文を読み解きながら、その真相に迫る。
目次
第1章 『原論』とはどんな本か
第2章 数学の論証スタイルの決定版―『原論』第1巻
第3章 幾何学vs.代数学―『原論』第2巻
第4章 初期ギリシア数学の歴史―『原論』の背景
第5章 図版はどう扱われたか―『原論』第3巻
第6章 解析という方法―『原論』第4巻
第7章 語られた数学と書かれた数学
第8章 比例の定義と非共測量―『原論』第5巻
著者等紹介
斎藤憲[サイトウケン]
1958年生まれ。1980年東京大学教養学部卒業(科学史科学哲学)。1982年東京大学文学部卒業(イタリア語イタリア文学)。1990年東京大学大学院理学系研究科博士課程(科学史科学基礎論)修了。理学博士。1992年千葉大学文学部助教授。1997年大阪府立大学総合科学部助教授。改組により2005年より大阪府立大学人間社会学部助教授(2007年より准教授)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
calaf
10
ユークリッドの『原論』って、もちろん名前は知っているものの、(こちらももちろん?)読んだ事はありませんでした。でも、詳しく読み込んでいけば、いろいろと分かってくるものなのですねぇ...それにしても、当時(紀元前数世紀)の人って、これを全て覚えていたのか... (驚)2012/09/22
Predora
4
そもそもユークリッド原論が何かを知らないで読んだが、なかなかに面白かった。数学の厳密な証明を積み重ねるスタイルの基になっていることや、現代人にとって読みにくい理由を時代背景から説明してくれたりと、数学以外の話にも触れているので途中で挫折せずに読めた。とは言っても中学数学までは理解できていないと読み進めるのは大変そう。2017/07/17
Amano Ryota
4
『原論』で採用された数学の記述方法が、その後の数学に与えた影響や、『原論』から読み解かれる、当時の数学の風景が、一般の読者にも分かりやすいように説明されていますので、そこだけ読んで、数学史の読み物としても十分楽しめる本だと思います。勿論、数学の歴史における『原論』の意義だけでなく、その中身にも触れられているので、数学書としての『原論』を読む入門用で、本書を手に取られても良いのではないかと思います。ただ、数学に全く縁のない生活を送っていると、紹介されている幾何学の命題で、ううっ!となってしまうので注意です。2015/07/05
guralis
2
古代ギリシアの数学というものがどんなものなのかについてふれることが出来た。なぜ言明がこんなにまどろっこしいのか、なぜ図版が今とは違うのうのか。目の前に書かれた具体的な図をもとに、対話しながら進めるという当時の数学のあり方が興味深かった。2016/09/03
フィ
2
子供の図形問題を解いている時に「三角形の内角の和は180°」という定理はどのようにして証明されるか?に疑問が生じて、突き詰めて調べたところ、ユークリッド「原論」に行きつきました。本書では「原論」の構成や解釈と当時の数学の考え方が解説されて参考になりました。今後も問題を解く際に「原論」を参照することになりそうなので、こちらの本も合わせて読み返すことにします。2013/12/07