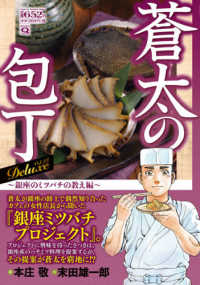出版社内容情報
生命はどのように誕生したか? ゲノムの科学の進展により、この永遠の謎も解明されつつある。本書は、人口細胞の合成や細胞内共生の再現など最新の研究を分かりやすく紹介。われわれの生命観がどのように変化したのかも解説する。
内容説明
進化工学的アプローチ、ゲノム構造の再編成から「生命らしい」システムの構築、進化の戦略までさまざまな方法論とアイデアで「永遠の謎」に迫る。
目次
1 生体高分子の進化工学(化学進化から分子進化へ;核酸の進化工学;タンパク質の進化工学)
2 ゲノム構造の再編成(ゲノム活用までの道のり;ゲノムの解析―現存ゲノムの多様性の理解;ゲノムの改変―再構築と淘汰(有用ゲノム獲得のための戦術、戦略)
ゲノムの活用―我々の英知と生活のために)
3 生命らしさを分子システムで再構築する(「生命らしさ」に迫る構成的アプローチ;生体膜モデルとしてのベシクル;外部とコミュニケーションするベシクル;生命はどのようにして動くか―自発運動するベシクル、エマルジョン;生命は情報を複製する;生命は自らも複製する―自己生産するベシクル)
4 表現型ゆらぎと適応・進化・共生への構成的アプローチ(「生物らしさ」とは;蛋白質濃度ゆらぎ;ゆらぎと環境適応;ゆらぎの進化;相互作用と共生)
5 ナチュラルヒストリーに基づいた生命観―生命倫理の現状と今後(生命の理解と倫理;古典的な合成生物学;最先端の合成生物学とナチュラルヒストリー;先端生命科学はどこまで行ってよいのか)
著者等紹介
浅島誠[アサシママコト]
東京大学特任教授、(独)産業技術総合研究所フェロー兼幹細胞工学研究センター長。専門は、発生生物学、生物の形づくりと器官形成
柳川弘志[ヤナガワヒロシ]
慶應義塾大学理工学部生命情報学科教授。専門は、分子生物学、蛋白質の進化工学
土居信英[ドイノブヒデ]
慶應義塾大学理工学部生命情報学科准教授。専門は、分子生物学
板谷光泰[イタヤミツヒロ]
慶應義塾大学先端生命科学研究所教授。専門は、分子生物学、合成生物学、ゲノムデザイン学
菅原正[スガワラタダシ]
東京大学大学院総合文化研究科複雑系生命システム研究センター特任研究員。専門は、物理有機化学、有機生命化学
四方哲也[ヨモテツヤ]
大阪大学大学院情報科学研究科教授。専門は、実験進化学、生物複雑系科学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
やす
incognito
mame0729