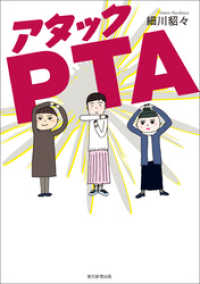内容説明
日本語学習者の疑問や誤りを手がかりに、日本人の頭の中にある「ことばのルール」をあぶり出す。私たちが日々、あやつっている複雑なルールの数々。
目次
1 はじめに―「母語」ではなく「外国語」として
2 「どうして「食べって」と言わないの」―説明は簡単じゃない
3 「そうですねえー、北京です」―文法は日々作られる
4 「先生、どうですか」―日本語にもお国柄
5 「先生は若いし、…」―ことばの背後に潜む文化や価値観
6 「今日はネコ暑いですね」―「わかりにくさ」を生みだすもの
著者等紹介
小林ミナ[コバヤシミナ]
1962年10月横浜市生まれ。1993年名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程(日本言語文化専攻)満期退学。名古屋大学助手、北海道大学助教授を経て、2006年から早稲田大学大学院日本語教育研究科教授。専門は日本語教育、とくに教育文法。「コミュニケーションを支える一要素」という観点から文法をとらえ、文法教育の方法や内容、そのために必要な文法記述について考えている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アイシャ
28
とても面白かった。目から鱗。日本語を外国語として見るなんて、考えたこともなかったから。これは自分の外国語習得の上でも、役に立つ考え方。作者が挙げる日本語習得上級者による間違いとその理由を解き明かす頭脳の明晰さ。こういう先生に当たれば、日本語習得中の方々本当にラッキー。日本語が喋れるからと言って、教えることが可能とは限らない。こうした腑に落ちない日本語例にぶち当たる度に、その背景を考えられる力がないと。文法的な間違いよりも、言語直観から判断したときの座りの悪さ。容認可能性の低い文、私もいっぱい失敗してる。2022/12/29
サアベドラ
9
日本語を学習中の外国人がよくやるミスを切り口に、日本語の文法・語法の奥深さに迫る。有り体に言うと、漫画『日本人の知らない日本語』をちょっとマジメにやってる感じ。文字がかなり大きく170ページほどしかないの数時間でさくっと読める。まあ面白いけど、ちょっと内容、分量共に薄すぎて物足りないですね。似たような本は他にも結構あるし。2013/10/07
atyang
2
「先生、今日はネコ暑いですね」や(授業後に生徒が)「あと、よろしくお願いします」などの、母語話者の自分からは思いつかない日本語の使用例が数多く紹介されている。この本の白眉は、それぞれの例に「なぜ日本語学習者がこのような使い方をしたか」が述べられている点だ。学習者の話す日本語を間違いとせず、学習者の中の独自の文法で語られているとする立場からこの書かれている。2016/10/24
みぽ
2
2016#51 気がつくと自然と身についている母語。読み書きは学習と練習を要するけれど、話す聞くは成長の段階で否応なく周囲の人間から自然と学びとっている。では、それを体系的に、そして理論的に他人に教えるとなったら…「いや、これはそういうもんです」ぐらいしか言えないんだろうな、私。ネイティブだから、その言語を教えられるというのは短絡的な考え方で、やはり指導者として勉強が必要なことが頷ける。日本語の間違いがどういうプロセスで起こったのか、掘り下げて理解する作業は、教える側にも教わる側にも大事だと思った。2016/09/01
水菜白菜椎茸昆布豆腐豚肉ポン酢
2
★★★★★2011/10/21