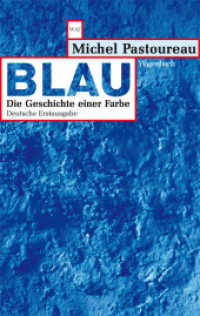内容説明
文献を通して見る日本語は、みやこの知識人たちのことば遣い。民衆が同じように話していたわけではないし、各地のことばが同じ歴史をたどったわけでもない。文献が覆い隠した民衆のことばを掘り起こし、独自の変化を遂げた中央語の系譜を探り当てる。―方言の視点から描く新しい日本語の歴史。
目次
1 日本語史の“当たり前”
2 常識から抜け出す方法
3 「こま」の常識
4 「くすりゆび」は書き間違い?
5 「おととい」の衝突
6 生きている「こそ」係り結び
7 東北方言「さ」の源流
著者等紹介
小林隆[コバヤシタカシ]
1957年、新潟県に生まれる。東北大学で国語学を学び、同大学院の博士課程に進む。1983年、国立国語研究所言語変化研究部第1研究室研究員。同主任研究官を経て、1994年から東北大学に勤務。東北大学大学院文学研究科日本語学講座教授。博士(文学)。第11回金田一京助博士記念賞(1986)、第23回新村出賞(2004)受賞。専門は方言学で、特に方言の視点から日本語の歴史を明らかにすることをテーマとしている。毎年、学生たちと調査に出かけ、方言の記録を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
288
著者の夢想の先にはトータルな日本語の歴史がある。すなわち、書き言葉として残された文献資料(『枕草子』や『源氏物語』、あるいは和歌や歴史書の類)だけではなく、話し言葉や中央(歴史的には京都、近代以降は東京)のではなく地方で話される言葉、あるいは支配階級ではなく庶民の言葉など、およそ全ての日本語を網羅することを庶幾しているのである。もちろん、それが夢のまた夢であることを重々承知の上で。ただ、幾分かのアプローチの方法がなくはない。その重大な手掛かりが方言である。もっとも、これまた扱いがいたって難しいのだが。⇒2023/07/07
サアベドラ
13
方言学の成果を日本語史に援用しようという試みを一般向けにわかりやすく説いた本。過去の文献資料ではわからない口語表現や地方人の言葉遣いを、現代の方言を細かく分析することで明らかにする。係り結びが九州で生き残っていたり、東北の「東京さ行ぐだ」の「さ」の由来が何であるかを解き明かしたりしている。本書を読むと、その時代の書き言葉がいかに地理的、階層的に限定されたものであるかを実感する。言語っておもしろいなあ。2013/08/04
Koning
3
気付けばあたりまえなのだけれど、気付かずにいることをはっきりと示してくれた良書。と言って良いと思う。こう考えると貴族から庶民までさまざまな階層の人物が個人的な記録を延々付け続けて来た日本の文化って偉大だ。2012/03/01
ゆり姐
3
☆☆☆☆ 「古文」に代表される日本語史、それが示すものは 「書き残されたことば」⇒「当時の権力の中心地での書き言葉」 時代が大きく変化するとき、言葉も大きく変化をする。 だけど、方言学の見地から見れば、それはただの、東西対立。 その証拠に、古文の時代の文法だと言われている2段活用は現代でも西日本で使われている☆ あの紫式部さえも使っていた「係り結び」も現代に残っている!! 「こそ」に代表される係り結びも、九州地方などに、方言として現在もその姿を残している!! また、方言周圏論を2011/02/27
yanapong
2
文献調査の質的・地理的限界の突破を方言調査で試みる日本語史。2012/02/09