出版社内容情報
特異な歴史家でラカンに忠実なフロイト派であったセルトーの関心は脱領域的だった.惰性化した文化の始源的活力を回復するために,マスメディア・広告・大学教育・暴力など日常的実践の意味を探る.
内容説明
惰性化した文化の始源的活力を回復するために、マスメディア・広告・大学教育・暴力などの日常的場面における意味と実践のかたちを探る。
目次
1 エキゾチズムと言語の分裂(「信じうるもの」の革命;都市のイマジネール;死者の美;暴力の言語)
2 新しい周縁主義(マス・カルチャーを前にした大学;文化と学校;マイノリティー)
3 文化の政治学(知の社会構造;社会のなかの文化;文化を論じる場所)
結論 空間と実践
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
87
難解。訳ゆえの難しさもあるだろうが、原文で読んだとて難しさにかわりはないだろう。文化を担うのが、知識人🟰大学であったところから、大学に誰でも入れるように改定され、公開講座を行ったり、ある程度の年齢になってから大学に入る学生を受け入れる(高度なカルチャー教室となってしまう懸念)ことで文化の大衆化が問われる。文化は誰のもの?そもそも文化はどこにでも存在していたのではないか?(民芸にみられるよなあ)等々、本著は問いかけてくる。質問自体をまだ理解し得ず、問いに対し問いたい始末‥。近々再読予定2024/07/17
-

- 電子書籍
- 訳あり秋くんの恋が聴こえる【単話版】(…
-
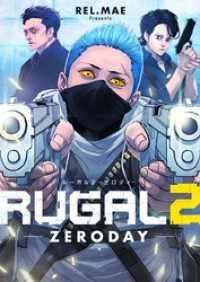
- 電子書籍
- ルーガル2 ーZERODAYー【タテヨ…
-
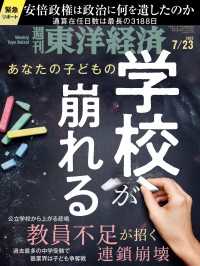
- 電子書籍
- 週刊東洋経済2022年7月23日号 週…
-
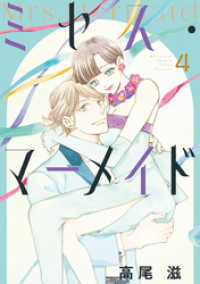
- 電子書籍
- ミセス・マーメイド【電子限定おまけ付き…





