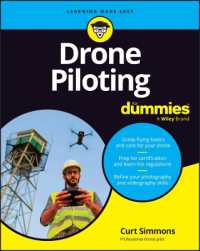出版社内容情報
元号という形で時間軸が変るのは,近代国家の中で日本だけである.歴史をさかのぼると,地域や時代によって,天皇との関わりは必ずしも等質的でない.南北朝に焦点を合せ,日本社会と天皇制の関わりをわかりやすく説く.
目次
1 天皇の存在を無視しては日本社会を論ずることはできない
2 日本社会についての常識を根底から問い直す(“島国のなかの単一民族”か?;“稲作のみが生業の中心”か?;“単一国家”だったのか?)
3 南北朝の動乱と天皇制(“遊女”の地位は低くなかった;“非人”は畏れ敬われていた;ピンチを迎えた天皇制;後醍醐天皇と文観;“異様な天皇制”)
4 現代とのかかわり
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
74
2016年795冊め。著者は「私は天皇および天皇制にたいしては徹底的に批判的な立場に立つものであります」と書いている通り、天皇制に疑問を投げかけるものである。ただ是非を問うというよりも、歴史の多角的な見方というものを示してくれているのでわかりやすい。農耕ではなく漁業から見る歴史だとか、天皇制と被差別部落だとか。2016/10/06
うえ
7
「日本の神々は、基本的に農耕神である、とくに稲作の農耕儀礼とむすびついて日本の神々の世界ができているのだということが、常識的には説かれておりますが、じつは日本の神様にささげる供物ー神饌ーのなかでは、コメや酒などの農産物の占める比重よりも、海で採れた海産物の占める比重のほうがはるかに大きい…カツオ、アワビ、あるいは海草、塩などの海産物が律令国家の時代から神々に大量にささげられております…渋沢敬三さんがあきらかにされていることなのですが、日本の神様はきわめて魚好きでありまして、現在でも…海のものを供える」2020/07/27
shigeki kishimura
6
"島国"という言葉によってガラパゴスな印象を与えられるけれど、そうじゃない。2021/03/19
KAZOO
6
網野先生の一般向けに書かれた小冊子です。先生の専門とされている分野をうまくまとめてこのような冊子の中にエキスをちりばめられたのはさすがであると思いました。この本によってさらにもっと深く勉強しようとする人が出てくれば先生も喜ばれたでしょう。2013/02/16
Hiroshi
4
日本ジャーナリスト会議主催の講演を加筆・再構成したもの。初版は昭和の時代。メインは、日本社会の常識を問いなおすとして、①島国の単一民族、②生業の中心は稲作、③単一国家 についてと、14世紀初めの南北朝動乱における後醍醐天皇のことが書いてある。対馬からは福岡と韓国が見え、特に韓国側はビルがわかるくらい近い。だから大陸との交流は盛んであった。これを担ったのが漁撈民であった。平安期の平将門の乱のように東日本と西日本は全く社会が違い、それが鎌倉幕府・鎌倉公方・江戸へと受け継がれた。天皇の権威とは別の権威があった。2016/12/17
-
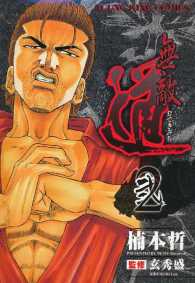
- 電子書籍
- 無敵道 (2)