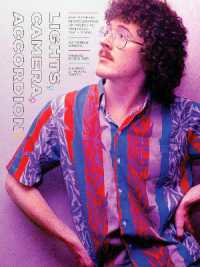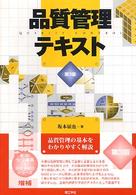出版社内容情報
徳川期から現代にいたるまで日本の経済思想はどう推移してきたか.今日の経済学はいかに多彩でまたいかなる可能性を秘めているか.熊沢蕃山から宇沢弘文,佐和隆光らに及ぶコンパクトな日本経済思想史像を提示する.
内容説明
日本の経済思想の多様な展開を幅広く概観。今日の日本の経済学はいかにして形成されたか、またどんな可能性を秘めているのか。外国人の目で、新鮮な日本経済思想史像を提示し、日本研究のパースペクティブを拡大する。単独執筆による通史である。
目次
序章 日本の経済思想と西洋の経済思想
第1章 徳川時代の経済思想
第2章 西洋経済思想の導入―明治維新から第一次大戦まで
第3章 両大戦間期の経済論争
第4章 戦後のマルクス経済学
第5章 経済理論と「経済の奇跡」
第6章 現代日本の経済思想
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
3
経済の本義は「経国済民」もしくは「経世済民」という「国を統治し、民を苦しみから救う」(23ページ)。この定義はいつでも思い出した方がいい。政治家がこれを忘れていることも多い。熊沢蕃山は奢侈と貧困は互いに関係しあっていると認識していた(27ページ)。石田梅岩は商人の道をして、人間本性の深い洞察を養成することを志向した(48ページ)。19世紀末において東大や京大、私立の慶大が西洋経済学の普及に努めていた(78ページ)。マル経近経(新古典派)を同時に日本に紹介した慶大の福田徳三の業績は大きい(114ページ)。2012/10/27
kotsarf8
0
戦後ある時期までの日本の経済学が非常にレベルの高かったことが分かる一冊。 恥ずかしながら初めて名を知った人も多い。篠原三代平それから後でも触れる大来の高度経済成長分析は是非とも読みたい。大内力の国家独占資本主義分析、長洲一二の構造改革論も、概略だけ読んでみても非常に魅力的だ。 筆者は[近代経済学]と[マルクス経済学]をどちらも学ぶことで、日本の経済学は米には見られない独自の視野を持つことができた、と述べているが、これは残念ながら過去の話なのだろう。 一番衝撃だったのは、官僚でもあり経済学者でもあ2013/01/19