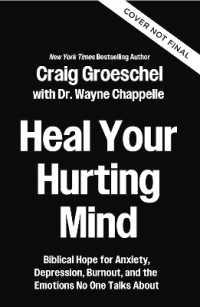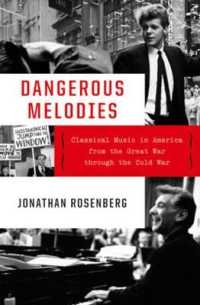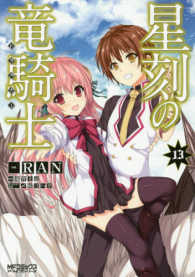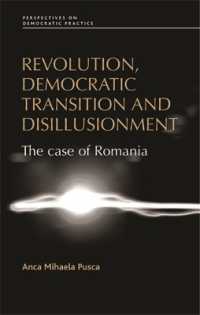出版社内容情報
小学校英語は「教科」になるのか。行政・学校・民間の関係者が激白!
小学生のパパ・ママ、先生たち、みなさんに読んでほしい本です
●臨場感あふれる激論を紙上で再現!●
文部科学省、教育委員会、小学校、大学教員、民間指導者、政治家が、それぞれの立場から小学校の英語活動・英語教育の現状を分析し、問題点を指摘。その解決策とあるべき姿を、熱く語る。
東京、大阪、名古屋、沖縄の4都市、4回連続シリーズで展開された文科省後援のシンポジウムをまとめたもの。
●おもな内容●
・小学校現場のさまざまな英語活動の問題点
・国際理解教育か英語教育か
・教科になったら、何がどうかわるか
・だれがどのように教えるか
・外部指導者に求められる資質とは
●印象的なひとこと●
・「ここ1年で必修化のめどをつけたい」・・・河村建夫(文部科学大臣)
・「英語活動をとおして、子どもの何を育むのかがポイント」・・・渡邉寛治(国立教育政策研究所 総括研究官)
・「小学校での英語教育を何のためにやるのか、理念を明確にすべき」・・・吉田研作(上智大学教授)
・「固定化された目標が『善さ』として、あらかじめどこかに存在していてはいけない」・・・村井実(慶應義塾大学名誉教授)
・「英語の時間はほめてもらえるから好き」・・・那覇市の小学生の言葉より
編:特定非営利活動法人 小学校英語指導者認定協議会(J-SHINE)
発売日:2004年5月26日
本のみ(195×135×24mm、264ページ)
[目次]
はじめに:『小学校英語の未来を探る』
吉田博彦(NPO教育支援協会代表、NPO小学校英語指導者認定協議会(J-SHINE)専務理事、
中教審外国語専門部会委員)
プロローグ:『小学校英語 必修化への道』
河村建夫(文部科学大臣)
第1部 提言:『小学校の英語教育を考える』
1・「早期英語教育政策 変革への兆し」
小池生夫(明海大学教授、慶應義塾大学名誉教授、J-SHINE理事)
2・「英語教育改革へのアプローチ」
吉田研作(上智大学教授、中教審外国語専門部会委員、J-SHINE認定委員長)
3・「国際理解教育の考え方、教え方」
中山兼芳(常葉学園大学外国語学部英語教育センター長、J-SHINE認定委員)
4・「児童英語教師が果たす役割」
仲田利津子(IIEEC代表、西部文理大学特命教授、J-SHINE認定委員)
5・「小学校英語を支えるNPO活動」
大河原愛子(ジェーシー・コムサ代表取締役会長、J-SHINE会長)
第2部 討論:『小学校の英語活動にどう取り組むか』(シンポジウム)
1.「教育現場の実情」
<東京会場パネリスト>
石村康代(新宿区教育委員会指導主事)
渡邉寛治(文部科学省国立教育政策研究所統括研究官)
松香洋子(松香フォニックス研究所代表、玉川大学講師、J-SHINE認定委員)
吉田研作(上智大学教授、中教審外国語専門部会委員、J-SHINE認定委員長)
<具体的内容>
・小学校の英語活動に求められるもの
・「英語を使おうとする態度」の育成が大切
・「積極性」を身につけた東京都新宿区の子どもたち
・指導者や学習のあり方をめぐる現場の課題
・小学校間の「英語力格差」をどうするか
・「言語習得を目的としない活動」の是非を問う
・「教育改革の一環」としての英語活動
・なくなりつつある「受験」の障壁
・学校の教育目標に見合った英語活動を
・民間の優れた英語指導者に期待
・指導者不足をどうするか―ALTの活用と教員研修
・小学校英語に取り組む人たちに望むこと
2.「教科としての英語の姿」
<沖縄会場パネリスト>
渡邉寛治(文部科学省国立教育政策研究所統括研究官)
松香洋子(松香フォニックス研究所代表、玉川大学講師、J-SHINE認定委員)
吉田研作(上智大学教授、中教審外国語専門部会委員、J-SHINE認定委員長)
中山兼芳(常葉学園大学外国語学部英語教育センター長、J-SHINE認定委員)
比嘉俊博(沖縄県那覇市教育委員会指導主事)
<具体的内容>
・英語活動の基本理念と「教科化」をめぐる課題
・「英語科」に取り組む那覇市の全小学校
・英語教育で子どもが変わる、先生も変わる
・小学校英語の可能性―小中連携とコミュニケーション教育
・コミュニケーション能力を高めるために
・小中連携に求められる「評価基準」
・教員交流や民間人材の活用を
・小中「対立」の構図から脱却するために
3.「国際理解教育との関わり」
<名古屋会場パネリスト>
梅村麻美子(名古屋市会議員、児童英語教室主宰)
加納幹雄(元文部科学省教科調査官、岐阜県立各務原高等学校校長)
中山兼芳(常葉学園大学外国語学部英語教育センター長、J-SHINE認定委員)
松香洋子(松香フォニックス研究所代表、玉川大学講師、J-SHINE認定委員)
<具体的内容>
・地方から日本の英語教育を変えていく
・在日外国人の力を活用する
・小学校の英語は「教科」になるのか
・求められる国家的グランドデザイン
・小学校と中学・高校の英語は違うのか
・「言葉」と「文化」をセットで学ぶ姿勢
・なぜ、「国際理解教育の一環」なのか
・「国際理解教育」が抱える課題
・英語活動から英語教育へ
4.「指導者の確保とALT活用法」
<大阪会場パネリスト>
巽俊二(大阪府羽曳野市立丹比小学校教頭、元大阪府教育委員会指導主事)
松香洋子(松香フォニックス研究所代表、玉川大学講師、J-SHINE認定委員)
中山兼芳(常葉学園大学外国語学部英語教育センター長、J-SHINE認定委員)
<具体的内容>
・ALTと日本人教師の役割分担
・英語力に自信を持てない日本の教師
・指導者不足の解消策―大阪の場合
・担任が主体となる指導が理想
・英語活動をテコに「学級革命」を
・ALTを生かしきれない日本の実情
・ALTと上手につきあうには
・指導助手としての外国人の必要性
・国際理解のための生きたリソース
・「納税者の目」で現実の課題を見る
エピローグ:『善く生きたい!- 子どもたちの声なき声を聞け』
村井実(慶應義塾大学名誉教授、アガトスの会(教育の原点を求める会)会長)
コラム:「ココが問題 日本の英語教育」
1.変わらない現実と求められる実行力
2.しっかりして先生! こんな授業はもういやだ
3.「研修」を生かすのは教師自身
4.ALTに聞いた「本音」の話
内容説明
子どもたちに英語力を!小学校英語は「教科」になるのか。行政・学校・民間の関係者が激白。
目次
はじめに 「小学校英語」の未来を探る
Prologue 河村建夫文科大臣が語る 小学校英語必修化への道
1 提言 小学校の英語教育を考える(政策面から―早期英語教育政策変革への兆し;教授法から―英語教育改革へのアプローチ ほか)
2 討論 小学校の英語活動にどう取り組むか(教育現場の実情;「教科としての英語」の姿 ほか)
Epilogue 村井実教授に聞く 善く生きたい!―子どもたちの声なき声を聞け
-

- 電子書籍
- 素人コスプレイヤー 猫子 - 本編