内容説明
とびきりの情熱。とびきりの貧乏。全身でぶつかって、この手でつかんだ芸術。よろこびも極上なら、悲しみも極上だ。おもいっきり生きた。思いっきり愛した。天才土方巽が蒼空に立ち上がるまでの、愛の胎内世界の饗宴。60年代舞踏神へのレクイエム。
目次
1 目をそむけないで 別れの時を
2 昭和の子供
3 アスベスト館の誕生
4 水たまりの水鏡
5 ふるさと―秋田
6 小町への道行
7 白塗りはこうして始まった
8 食べられるオブジェ
9 ズボーノ氏たちのダンス
10 肉体の叛乱
11 挫折を越えて
12「燔犠大踏鑑」
13 「東北歌舞伎」まで
また逢う日まで
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
12
書庫整理中に再読。夫が生前の彼女の公演に参加した時期があって、懐かしく読んだ。「舞踏」の定番である白塗りが、土方が背中の傷を隠すために始めたのよ、と彼女から聞いたっけ。不思議な気持ちになったのを覚えている。個人的には彼女は舞踏家ではなかった気がするけれど、もっとリスペクトされてもよかったダンサーだと思う。2018/02/28
misman
2
図書館で借りた本。土方の生涯の中で一番近くにいた方の証言。踊りが生まれた理由は単純ではないということを改めて思う。土方の生まれ育ちや時代、周囲の人々といった一つ一つの糸が複雑に絡むことで奇跡的に生まれたような感じがした。そのような奇跡を引き寄せることが出来たのが土方なのだとも思う。実際に見ることは出来ないが、表現への凄まじい熱烈な情熱は感じた。2020/01/29
miracolo
0
印象深かったのは、妻であり著書の元藤さんの、肉体について言ってる「対象に直線的に達する日常の動作のごときはとりも直さず労働と能率の囚人にほかなるまい」って発言。自分の解釈では、何かの目的の為にその動作をする、例えばペン立てのペンを取るために手を伸ばすとか。それの反対で思い付くのが、無目的に身体を動かす、身体との対話、身体への意識と無意識のさじ加減?とかそれ位。舞踏はとても興味深い。 「ロシア革命の発火点はニジンスキーの肉体にあってレーニンの脳髄にはない、という逆説は不可能だろうか?」この考え方好きだな2014/09/12
-
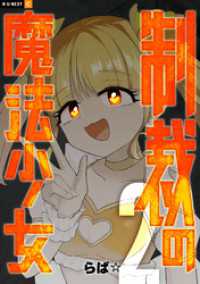
- 電子書籍
- 制裁の魔法少女 2巻 U-NEXT C…
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】黄泉の蜜なる神隠し5 C…
-

- 電子書籍
- 毎日のドリル はじめてのプログラミング…
-

- 電子書籍
- 恥をかかないスピーチ力 ちくま新書














