内容説明
被差別部落、性差別、非・常民の世界―日本民俗学が避けてきた穢れと差別のテーマに多方面から迫り、民俗誌作成のための基礎知識を提示。
目次
1 民俗研究と被差別部落
2 差別の生活意識
3 性差別の原理
4 シラとケガレ
5 ケガレの民俗文化史
6 今後の課題
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ジャズクラ本
12
◎1996年刊行。民俗学の本は柳田をはじめとして明治の文体で読み辛いが、これは文体で難儀しなくていいのが有難い。しかも非常に面白い。後半は少し難。/谷川士清「倭訓栞」/原田信男「歴史のなかの米と肉」/近年新「海上の海」として赤飯と赤米の再検討がなされ始めた/神社が食肉をケガレとして祭りの際に排除するのは日本に限らず東アジアの諸民族においても同様/沖縄には食習慣として獣肉があった。本土は餅正月だが、沖縄は豚正月となる/小林初枝「被差別部落の世間ばなし」/柳田国男「郷土生活の研究法」/盛田嘉徳「河原巻物」2019/10/31
mogihideyuki
1
ケガレとは日常世界のバランスが崩れた状態のことであって、後に不浄や汚らわしいという意味が付与されていったという。日常生活空間=ケゴ(藝居)の中心には主婦が管理するケシネビツ(米櫃)があり、米が充足されなくなることがケガレ(ケ枯レ)であった。この時点ではケガレに関わる女性は神聖で畏怖されるものであり、蔑まれてはいない。後に被差別部落につながる屠畜や皮革仕事も、皮剥ぎ=生まれ変わり=増殖の力に関わるとされ、特別な力を行使する人々だった。この「カワタ」の人々が穢多と呼ばれるようになるのは17世紀のことだという。2018/08/08
とまる
1
女性を崇めていた日本人が女性を穢れているとし始めたのは、その性別のためか血との関連深さのせいか。そこを掘り下げるだけでも古代宗教に詳しくなれそう。また、女性から離れ「エンガチョ」についても語られているが、子どもの遊びには差別と繋がる普遍的なイメージが潜んでいる。例えば、糞を踏んだりして「穢れた」子にタッチされると伝染する。子どもっぽい発想だが不可触民という言葉もコレとあまり変わらない。私的には、併せて挙げられている「汚ならしいものに、かえってパワーがある」という話も面白い。2012/04/21
-

- 電子書籍
- シンデレラは嘘をつく【タテヨミ】 18…
-

- 電子書籍
- ずっと、ずっと好きだった―再会愛―3 …
-
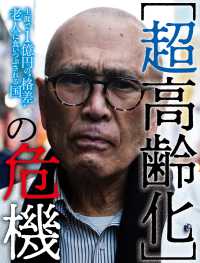
- 電子書籍
- 超高齢化の危機 SPA!eセレクション
-
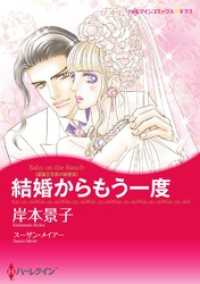
- 電子書籍
- 結婚からもう一度〈富豪三兄弟の秘密II…
-
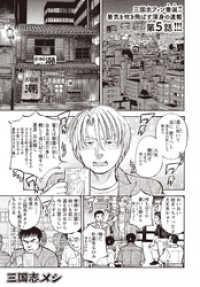
- 電子書籍
- 三国志メシ 5膳目 コミックトム




