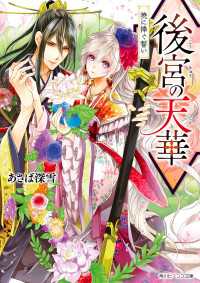感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
7
芸術様式の発展を作品自身に見ようとしたAリーグルを念頭に置いた著者は、飛鳥白鳳期以来の日本建築が拘る柱を神の依代とせず神自身の実体とし、建築を神人同席の場と捉えた。本書ではこの「実体」傾向の強い寺社建築の構成を主体の占有空間が中心の「彫塑的」構成と呼ぶ。一方平安期以後構成は「絵画的」となり、建築の正面に客体としての中庭、客体としての内部空間(礼堂)が建築を複合化し、安土桃山期には主体の動きを前提とした行動的空間構成に変わるとする。著者は日本建築の発展を、西洋の空間の幾何学的統合と異なる断片化として捉える。2025/08/04
さくら
1
以前、「チラリズムは日本人にしか理解出来ない趣味なんだよ!」という話を聞いていたのだが、本書の最終的に日本人は空間を断片化するようになったというまとめでより納得した。一度に全てを見せるのではなく、断片的に見せるとかまさにチラリズムじゃないですか!2013/09/16
powe
0
日本建築が時代に伴って、どのように変化していったのかがよくわかる。 彫塑的な寝殿造から行動的空間を優先した書院造りへ。 ちょっと古い日本家屋とから見ると、屋根の掛け方がむちゃくちゃなものがあるけと、あれは内部を優先してるんだなと納得。2020/02/07