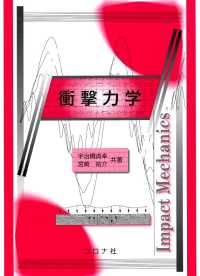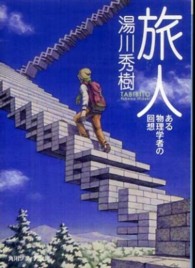出版社内容情報
人と自然の関係が変わる!
生態系を回復させ、温暖化まで止める
「奇跡のカーボン・ファーミング」とは?
有効な温暖化対策「カーボン・ファーミング」としていま脚光を浴びるリジェネラティブ(環境再生型)農業。その第一人者による初のノンフィクション。
4年続いた凶作の苦難を乗り越え、著者が自然から学んだ「土の健康の5原則」。そこには、生態系の回復や カーボン・ファーミングのエッセンスが凝縮されている。地中の生態系のはたらきを阻害さえしなければ、あらゆる土が真に「生きた土」に変わる。さらに、やせた土地の回復は、農業の衰退、食料危機、環境破壊、気候変動問題などの対策にもつながるのだ。
21世紀のさまざまな課題解決の糸口となり、自然への見方が変わる、野心的な〈土壌のバイブル〉!
各氏絶賛!
米アマゾンで1000を超える5つ星レビューを獲得!
「土は生命現象の産物、そして生命のゆりかご。土から始まる環境革命の実践書」福岡伸一(生物学者)
「人が土を育て、土が人間を育てる。土をケアする営みは、こんなにも奥深く切実で面白い」森田真生(独立研究者)
内容説明
有効な温暖化対策「カーボン・ファーミング」としていま脚光を浴びる環境再生型農業。その第一人者が、4年連続の凶作を乗り越えた末に自然から学んだ「土の健康の5原則」には生態系の回復やカーボン・ファーミングのエッセンスが凝縮されている。地中の生態系のはたらきを阻害さえしなければ、農園から家庭菜園、ガーデニングまで、あらゆる土が真に生きた土に変わる。さらに、やせた土地の回復は、農業の衰退、食料危機、環境破壊、気候変動問題などの対策にもつながるのだ。21世紀のさまざまな課題解決の糸口となり自然への見方が変わる、野心的な“土壌のバイブル”!
目次
第1部 道のはじまり(絶望からの出発;自然がよみがえる;リジェネラティブの気づき;牛が牛でいられるように;次世代に引き継ぐ;ブランドをつくり出す)
第2部 理想の「土」を育てる(土の健康の5原則;カバークロップの偉大な力;土さえあればうまくいく;収量よりも収益を)
著者等紹介
ブラウン,ゲイブ[ブラウン,ゲイブ] [Brown,Gabe]
気候変動対策「カーボン・ファーミング」として、いま世界で注目を集めるリジェネラティブ農業(環境再生型農業)の第一人者。アメリカ、ノースダコタ州で2,000ヘクタールの農場・牧場を営む。妻と息子の家族3人でたび重なる危機を乗り越えて、化学肥料・農薬を使わない不耕起の栽培によって、自然の生態系を回復させる新たな農業を確立した。彼の農場には国内外から毎年数千人の見学者が訪れるほか、講演やメディア出演も多数行い、世界中にそのメソッドを伝えている。アメリカ不耕起栽培者賞、天然資源保護協議会から成長グリーン賞を受賞
服部雄一郎[ハットリユウイチロウ]
翻訳家。UCバークレー公共政策大学院修了。「ゼロウェイスト」や「プラスチック・フリー」の実践的な取り組みがメディアで紹介され注目を集める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
yyrn
Daisuke Oyamada
Sakie
Yutaka Matsuzawa