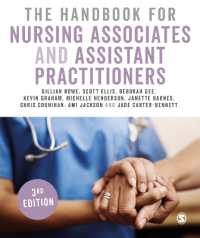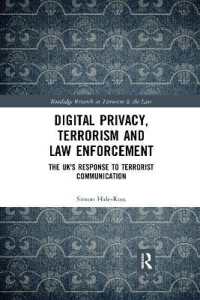出版社内容情報
『白い巨塔』『華麗なる一族』ほか、執筆秘話を明かすー。なぜ財前は二番で敗れたのか?万俵頭取にモデルはいるのか?待望の全3巻シリーズ、第二弾!
内容説明
なぜ財前教授は、二審で敗れたのか?万俵頭取親子に、モデルはいるのか?政界財界学界、困難な取材にはどう挑むか?戦後のあの日あのとき、作家は何を考え、何を取材し、何を書こうとしたのか。デビュー作、直木賞受賞作など、大阪を舞台にした作品の“謎”が明らかに。山崎文学50年の総決算。
目次
第1章 『花のれん』、『白い巨塔』他―自作を語る(産声;ああ、もったいなぁ成駒屋はん;“土性っ骨”のある男に惚れる ほか)
第2章 あの人やつしやなあ―大阪あれこれ(小遣帳;庶民の味;上方贅六 ほか)
第3章 半年勉強、半年執筆―私の小説信条(植林小説;取材方法と小説作法;不在のデスク ほか)
著者等紹介
山崎豊子[ヤマサキトヨコ]
1924(大正13)年、大阪市生れ。京都女子大学国文科卒。毎日新聞大阪本社学芸部に勤務。当時、学芸部副部長であった井上靖のもとで記者としての訓練を受ける。勤務のかたわら小説を書きはじめ、1957(昭和32)年に『暖簾』を刊行。翌年、『花のれん』により直木賞を受賞。新聞社を退社して作家生活に入る。1963(昭和38)年より連載をはじめた『白い巨塔』は鋭い社会性で話題を呼んだ。『不毛地帯』『二つの祖国』『大地の子』の戦争三部作の後、大作『沈まぬ太陽』を発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
rena
じゅんじゅん
ほっそ
い
のりたま
-

- 電子書籍
- 死がふたりを分かつまで11巻 ヤングガ…