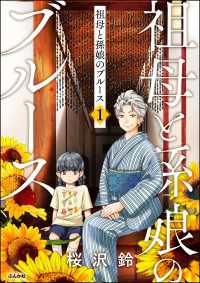出版社内容情報
常に自然科学としての心理学をめざしたジェームズ(一八四二―一九一〇)は,心理学の目的を,意識状態(心的状態)そのものを記述し説明することであるとし,その説明のために,意識状態の原因,条件,結果などに関して,意識状態と内外の関係を支配する法則を発見することを論じた.主著『心理学原理』の短縮版.索引を付す.
内容説明
常に自然科学としての心理学をめざしたジェームズは、心理学の目的を、意識状態(心的状態)そのものを記述し説明することであるとし、その説明のために、意識状態の原因、条件、結果などに関して、意識状態と内外の関係を支配する法則を発見しようとした。主著『心理学原理』の短縮版。
目次
感覚総論
視覚
聴覚
触覚、温度感覚、筋肉感覚、痛覚
運動の感覚
脳の構造
脳の機能
神経活動の一般的条件
習慣
意識の流れ
自我
注意
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ジョンノレン
52
「プラグマティズム」ではご都合主義的かつ宗教傾斜に幻滅したが、この「心理学」は一貫して自然科学的アプローチで好感。前半の感覚知覚や脳の諸機能についても最新知見とは比較できないが世紀後半には解剖学側面は勿論神経伝達を含めかなり解明が進んでいた事を伺えた。習慣の重要性や意識の4つの構造(状態、変化、連続、選択)など基本オーソドックス。「意識の流れ」や「自我」はやや思考実験的かな。主我と客我に分けたり、自尊心=成功/願望なんて式や西田も取り組んだ自己同一も。意識の範囲として「注意」も独立の章として語られる。2025/08/13
Ryosuke Tanaka
2
1892年時点で神経解剖学がここまでわかっていたのかというのは驚き。フェヒナーが無下に無価値とされてしまっているのはちょっと意外。習慣のはなしがかなりマッチョな人生訓に直結しているところはさすがプラグマティズムという感じなのか。2016/11/10
Hiroki Hatano
2
人の気持ちや判断ってどのように選択・決定されるのか知りたくて、心理学をかじりはじめた。基本はWeb講義(Coursera)を受講しているが、理解を補足するために、引用されていた本を読んでみた。前半の説明(視覚・聴覚・脳などがどのように外からのインプットに反応するか)はちょっと難しかったが、後半の説明(習慣、自我、注意等インプットをどう処理するか)は実例を交えており、興味深かった。心理学は想像どおり奥が深く、付け焼刃でも概要を説明できるようになるには、もう少しいろいろ関連する本を読みこまないと無理と感じた。2013/08/20
6ちゃん
2
古い本なので今では間違っている記述が多々あるが、人の心理現象を科学的に使おうとした精神が伝わってくる。脳の解剖からスタートしている点はむしろ現代的とも言える。心理学を学ぶ人は一度は読んで欲しい。
のほほんなかえるさん
0
いわゆる分析的手法により「心」へ外側から攻め込んでいく。ベルクソンとの比較も念頭に置いて読む分、違いも際立つ。2011/02/16