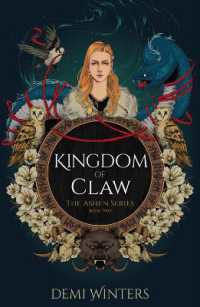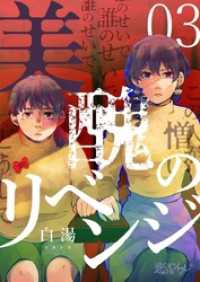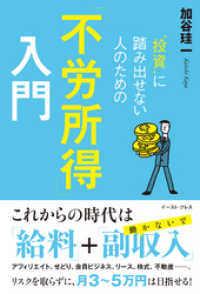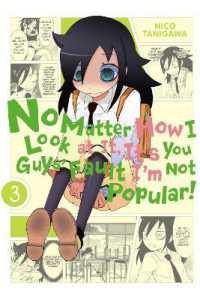内容説明
福澤諭吉の思想的バックボーンを、ジョン・スチュアート・ミルとの対話を軸に縦横無尽に深掘りする、知的興奮に満ちた講演録。
福澤諭吉が読み込んだ洋書に残された自身の書き込み、貼付した付箋等を手がかりに、福澤諭吉が西洋思想をいかに自家薬籠中のものとしていったのかを探る、安西教授熟練の知的検証作業。
「福澤がその論説を著すに当たって依拠したであろう洋書に見られる数々のノート、書き込みや不審紙ないし付箋の貼付など……その重箱の隅を楊枝でほじくるが如き詮索作業の一部」本書「はじめに」より
目次
まえがき
一 はじめに
二 実学(サイエンス)と技術(アート)
三 功利論(ユーチリタリヤニズム)と正義
四 自由(リベルチ)と独立(一)――「一身独立」
五 自由(リベルチ)と独立(二)――「一国独立」
六 おわりに――思想的位相
註
福澤諭吉とJ・S・ミル関連年表
あとがき
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
2
実に就くを以て先とする 一身恰も真理原則の塊たらん 科学が進歩すれば技術の領域が狭くなる 学者は社会の奴脱を以て自から任ずる者 学問上の学者と実業の学者 サイエンスの修得が自由を育む 不撓独立の士 智徳事業の棚卸 文明の弊害 自由の気風は唯多事争論の間に在て存するもの 人たる者の分限を誤らずして他を凌ぐとき 東洋の数理と独立心 文明と野蛮の戦争 人の命を視るにあらざるもの 小国を助ける権力は権力の平均 ノープルフイーリング 最大幸福の旨は苦痛を去り楽に進むに在り 虚飾を尚ぶの起源は人を制御せんとするに在る2025/05/10