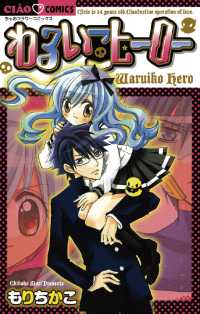- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
いま、日本社会は停滞の渦中にある。その原因のひとつが「労働環境の硬直化・悪化」だ。長時間労働のわりに生産性が低く、人材の流動性も低く、正社員と非正規労働者のあいだの賃金格差は拡大している。 こうした背景を受け「働き方改革」が唱えられ始めるも、日本社会が歴史的に作り上げてきた「慣習(しくみ)」が私たちを呪縛する。 新卒一括採用、定期人事異動、定年制などの特徴を持つ「社会のしくみ」=「日本型雇用」は、なぜ誕生し、いかなる経緯で他の先進国とは異なる独自のシステムとして社会に根付いたのか? 本書では、日本の雇用、教育、社会保障、政治、アイデンティティ、ライフスタイルまで規定している「社会のしくみ」を、データと歴史を駆使して解明する。【本書の構成】第1章 日本社会の「3つの生き方」第2章 日本の働き方、世界の働き方第3章 歴史のはたらき第4章 「日本型雇用」の起源第5章 慣行の形成第6章 民主化と「社員の平等」第7章 高度成長と「職能資格」第8章 「一億総中流」から「新たな二重構造」へ終章 「社会のしくみ」と「正義」のありか
目次
第1章 日本社会の「3つの生き方」
第2章 日本の働き方、世界の働き方
第3章 歴史のはたらき
第4章 「日本型雇用」の起源
第5章 慣行の形成
第6章 民主化と「社員の平等」
第7章 高度成長と「学歴」
第8章 「一億総中流」から「新たな二重構造」へ
終章 「社会のしくみ」と「正義」のありか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
149
2020年新書大賞第5位。 学歴重視・勤続年数重視の日本社会の 特異性、慣習の束 を描いた作品である。 「正社員になり定年まで勤め上げる」という 生き方 …日本に現存する 暗黙のルールを 歴史的に掘り起こす …「カイシャ」と「ムラ」に帰属する日本の 特徴を わかりやすく描いている、そんな本だった。2020/06/03
KAZOO
130
新書で書かれているのですが内容的には選書やハードカバーであると感じました。それと題名が日本社会とはいうものの分野的には雇用関連の話が中心を占めています。かなり過去の文献を読みこんでおられてそれなりに参考となるのですが分析にとどまっていて今後の方向性や政策に参考となるものをもう少し示してほしい気がしました。2019/11/23
ねこ
129
日本社会のしくみを構成する原理の二つの重要な要素がある。①学校(大学)で何を学んだかが重要ではなく、どの大学に行ったか②1つの組織(会社)での勤続年数長さ。これに加えて3つの型がある。所得が比較的多い「大企業型」、収入はそれほど多くないが地域の人間関係が豊かな「地元型」、最後に収入も少なく地域に足場もない「残余型」。昭和の時代はこうだったが、平成、令和と来て今は正規と非正規の二重構造。日本は先進国な中で残念ながら最も貧乏な国になってしまった。2030年代、私達はふたたび豊かな国になるため今何をすればいい?2025/04/25
佐島楓
83
労働史を概観することでこの国の雇用のしくみを読み解くもの。先行研究を多く参照し、データを使いながらシャープな論理を展開している。新書で約600ページとかなりの分量なので本当に興味のある方しか手に取れないかと思うが、欧米との雇用形態の比較もあるため、しっかりとした知見を身につけたい方におすすめしたい。2019/07/20
trazom
79
日本の雇用制度を、その歴史的背景に鋭く踏み込んで分析した力作である――小熊先生の本は、いつも粘着力の強い「力作」だけれど…。欧米社会が「職務の平等」を目指したのに対し、日本の労働者は「社員の平等」を求める。日本独自の雇用環境を成立させたのが、政府や経営者以上に、労働者自身であったことが面白い。経営の恣意を排し、客観的なルール(勤続年数、学歴など)に基づく処遇で「平等」を求める労働者と、何があっても企業横断的なルールを避けたい経営者たちの妥協の産物が「日本社会のしくみ」だったのかもしれない。2019/09/27