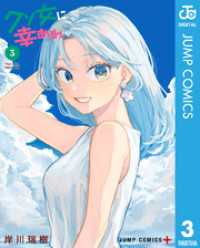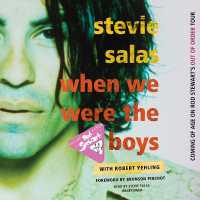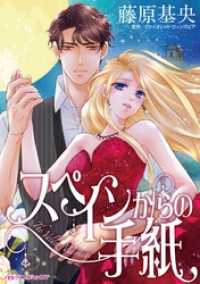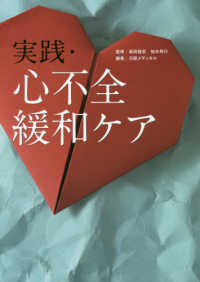- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
西洋哲学と出会って150年、日本の哲学者たちは何を考え、何を目指してきたのか。日本哲学のオリジナリティに迫る、第一人者による入門書の決定版!
【哲学を知るための10講】
第1講「日本の哲学」とは/第2講 哲学の受容第/3講 経験/第4講 言葉/第5講 自己と他者/第6講 身体/第7講 社会・国家・歴史/第8講 自然/第9講 美/第10講 生と死
【本書のおもな内容】
・日本最初の哲学講義はいつ行われた?
・「哲学」という呼び名はこうして生まれた
・西田幾多郎の「純粋経験」を知る
・経験と言葉のあいだにあるもの
・言葉の創造性を考える
・人間の生のはかなさと死に迫る
・心によって生かされた身体とは
・田辺元が生み出した「種の理論」
・「自然」という言葉の歴史
・和辻哲郎の「風土論」
・美とは何か、芸術とは何か
・移ろうものと移ろわぬもの
・光の世界と闇の世界