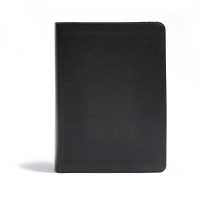出版社内容情報
【内容】
本書は、「都市の国」であるイタリアの地域社会がどのようにして、形成・確立したかを研究したものである。具体的には、興隆してきた北イタリアの都市コムーネが12世紀後半、帝国の再建に粉骨砕身するフリードリッヒ=バルバロッサと戦いつつ、「政治的独立」を達成していく過程(第1部第1章~5章、付録)と、その都市コムーネが司教に代わってどのようにして農村領域を集約し、地域に深く根を下ろしていったか、その領域支配の確立過程(第2部第6章~10章)を明らかにする。第24回マルコ・ポーロ賞受賞。
【目次】
序 イタリアの中世都市と研究課題
1 帝国内における都市コムーネ体制の確立
――フリードリッヒ=バルバロッサとイタリア諸都市
1 『フリードリッヒの事績』にみるイタリア支配の論理
2 バルバロッサとミラノ市
3 バルバロッサに破壊された中・小都市
4 バルバロッサと小都市ローディ
5 バルバロッサに対抗するロンバルディア都市同盟
2 領域内における都市コムーネ体制の確立
6 司教と都市――司教の世俗的支配権の実態
7 国王証書にみる司教と都市コムーネ
8 領域支配権の司教から都市コムーネへの移行
――12・3世紀中部イタリアの中都市ピストイアの農村支配の分析から
9 中都市の都市条例にみるコムーネ体制
――ピストイアの12世紀と1296年の都市条例の分析から
10 都市コムーネによる領域支配の確立――ピストイアの農村ポデスタ制
付 録 フリードリッヒ=バルバロッサとイタリア諸都市に関する研究史
あとがき/フリードリッヒ=バルバロッサとイタリア諸都市関係略年表/主要文献目録/人名索引
内容説明
本書は、「都市の国」であるイタリアの地域社会がどのようにして、形成・確立したかを研究したものである。具体的には、興隆してきた北イタリアの都市コムーネが12世紀後半、帝国の再建に粉骨砕身するフリードリッヒ=バルバロッサと戦いつつ、「政治的独立」を達成していく過程と、その都市コムーネが司教に代わってどのようにして農村領域を集約し、地域に深く根を下ろしていったか、その領域支配の確立過程を明らかにする。
目次
イタリアの中世都市と研究課題
第1部 帝国内における都市コムーネ体制の確立―フリードリッヒ=バルバロッサとイタリア諸都市(『フリードリッヒの事績』にみるイタリア支配の論理;バルバロッサとミラノ市;バルバロッサに破壊された中・小都市;バルバロッサと小都市ローディ;バルバロッサに対抗するロンバルディア都市同盟)
第2部 領域内における都市コムーネ体制の確立(司教と都市―司教の世俗的支配権の実態;国王証書にみる司教と都市コムーネ;領域支配権の司教から都市コムーネへの移行―12・3世紀中部イタリアの中都市ピストイアの農村支配の分析から;中都市の都市条例にみるコムーネ体制―ピストイアの12世紀と1296年の都市条例の分析から;都市コムーネによる領域支配の確立―ピストイアの農村ポデスタ制)
フリードリッヒ=バルバロッサとイタリア諸都市に関する研究史
著者等紹介
佐藤真典[サトウシンスケ]
1942年天津市に生まれる。1964年広島大学教育学部卒業。1971年広島大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。1971―3年イタリアScuola Normale Superiore di Pisaに留学。現在広島大学教育学部教授、中世イタリア史専攻、博士(文学)。主著に「中世イタリアの司教の世俗的支配権」竹内正三、坂田昭二編『ローマから中世へ』渓水社、1985年所収。「都市国家の成立―帝国と都市―」清水広一郎、北原敦編『概説イタリア史』有斐閣、1988年所収。「中世からルネサンスにかけてのイタリアの都市のイメージ―「都市美観の誕生」試論―」斉藤稔編『諸芸術の共生』渓水社、1995年所収。翻訳にN.オットカール著『中世の都市コムーネ』(清水広一郎共訳)創文社、1972年
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
富士さん
-

- 電子書籍
- 高齢出産ドンとこい!!(分冊版) 【第…